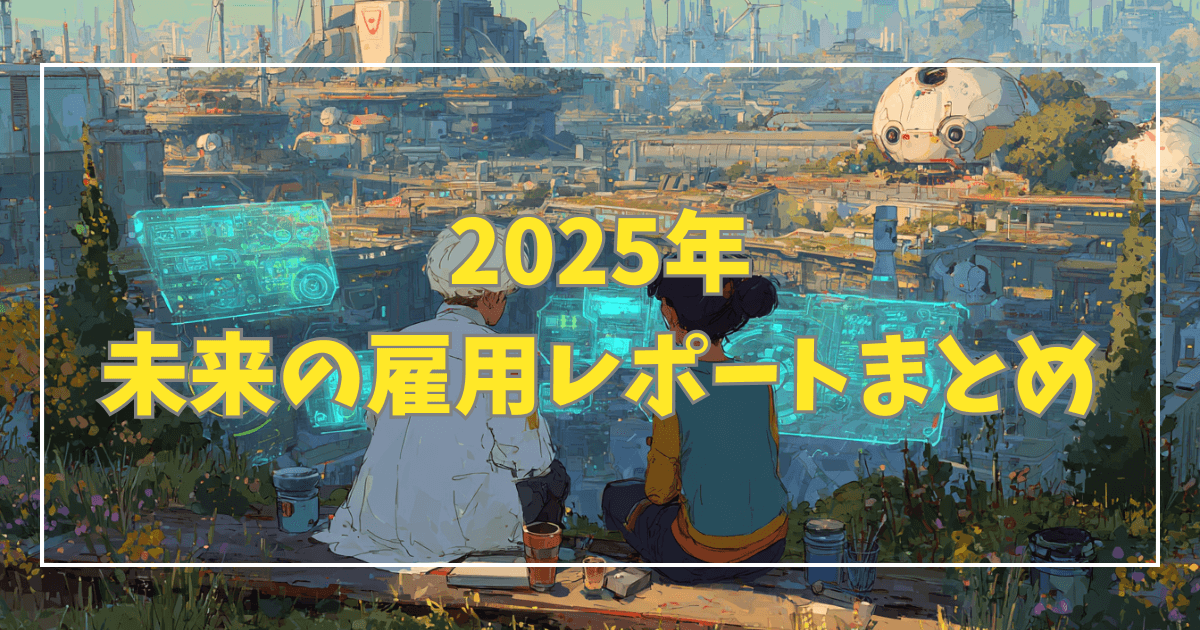
この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「【2025】未来の雇用レポート」を再構成した内容をお届けします。

本記事では、2030年へ向けた「増える仕事」と「何を学ぶべきか」を整理します。ぜひ、以下の記事と合わせてお読みください。

―― 前回はレイオフの話でしたが、今日は増える方の話なんですね。
「はい。前回はレイオフのお話したと思うんですけども、これはどんどん減っていくっていうお話だったじゃないですか。今日はですね、増えるよっていう話をしていきたいなと思います。」
世界経済フォーラムのレポートとは
―― まず今回のレポート、どういうものなんですか。
「これはですね、世界中の雇用主を対象にした調査で、1,000社超が回答し、合計1,400万人以上の労働者を代表する形になっています。22の産業クラスターと55の経済圏をカバーし、2025年から2030年の動向を見ています」
―― 結構規模大きいですね。
「はい。ミクロ的な点はちょっとわかんないんですけど、マクロで見れば大きくは外さないんじゃないかと思ってます」
―― やはりAI職種が伸びるの?
「言うまでもなくAI関連の仕事は%で見ると、とてつもなく増えています。ただ絶対数で見るとどうかっていうと、また違うんですよね。%でめっちゃ増えてますってことは、元が少ないから。ちょっと増えただけで、1000%増えましたとか言えちゃうんですよ。でも、元々たくさんあるところは、絶対数で見たら違うよねって当たり前じゃないですか。」
―― つまり、率ではなく量で見ないと本質はつかめない。
「そうですね。そこで、この報告書では、調査対象企業の推計と国際労働機関の雇用データを組み合わせて、純増と純減が最も大きい15の職業を挙げています。どんな仕事が実際に増えるのかが分かるということですね。」
1位:農業従事者
―― 最も成長が著しい職業は、農業従事者だそうですね。
「そうなんですよ。農業。AIからかけ離れてるような気がしますけどね。これはですね、二酸化炭素排出量の削減や気候危機への適応といったグリーントランジションによって、2030年までに約3400万人の新規雇用が生まれる見込みという話です」
―― なるほど。
「さらにデジタルアクセスの拡大、生活費の上昇も含めて、この職種の成長に貢献するのではないかと。」
―― 生活費が上がるから農業従事者が増える?
「インフレのことを多分言ってると思うんだけど。農業が拡大していけばその生活賃金のベース上がるよねって話なんじゃないかなと※1」
※1 生活費上昇が直接農業雇用を押し上げるのではなく、食料価格の上昇が生産の採算を引き上げ、各国の食料安定策が生産拡大を後押しするようです。ただしWEFの文脈では主因はグリーントランジションのため生活費上昇は補助的要因です。
2位:配達ドライバー
―― 続いて2位は配達ドライバーですね。
「はい。ドライバー職です。Amazonの配達員とか、トラックの運転手とかですね。」
―― 自動化やドローンの話も多い中で、意外に増加なんですね。
「そうなんですよ。最近、Amazonが配達員向けにAIスマートグラスを開発中と発表していて、スマホでの検品や確認作業をグラスで完結できるようにする。荷物を持つだけで、どこに届けるかが視界に表示されるような仕組みですね。」

―― 未来的ですね。
「そう。これが実用化されると、1人が運べる荷物量が増えて効率化される。結果的にAIによって仕事が減るというより、AIを使う人が増える方向なんです。」
―― ドローンや自動運転よりも、現場を支えるAIの形が先に来る感じですね。
「そう思います。ドローン配達や完全自動運転はまだ制度やコスト、安全面の課題があります。だから2030年までは、人がAIやデバイスを活用して仕事量を増やす形が中心だと思います。」
―― なるほど。まだ現場は安定していると。
「そうですね。インフラが整うまでは人の需要が続くはずです。」
3位:ソフトウェア開発者
―― 3位はソフトウェア開発者です。これは少し意外です。
「そうですよね。AIでコーディングが自動化されるのに、数は増えるという結果です。」
―― どういう背景なんでしょうか。
「普通に考えたら減りそうですが、それ以上に増える要因があるんです。新しいアプリやツールが増えて、開発・運用・保守の仕事が拡大してる。特にセキュリティの需要がすごく高まっています。」
―― セキュリティですか。
「はい。最近は各社からAI搭載ブラウザなどの新しいプロダクトも出ていて、セキュリティの話題が増えてますよね。新しい技術が出たばかりの時期って無法地帯なんです。最初に車ができた時もシートベルトがなかったように、後からガードレールや安全装置が整っていく。その過程で安全を作る仕事が増えるんです。」
―― なるほど。AIの進化が早い分、守る側の仕事も急増する。
「そうです。だからコーディングは終わりだという話もありますけど、マクロに見ればむしろ増えていく。生成AIが開発を効率化するほど、新しいプロジェクトが立ち上がり、運用やセキュリティの仕事が増えるという構図ですね。」
―― 開発スピードが上がるほど、作る・直す・守るが増える。
「そう。開発者はコードを書く人から、価値と安全を運用で担保する人に役割が広がっていく。だから全体の人数としてはむしろ増えるのではないかと考えています。」
4位:建設作業員
―― 続いて4位は建設作業員ですね。
「はい。これは納得ですね。建設業はやっぱり人手が必要なんですよ。」
―― ホワイトカラーはAIに置き換わりやすいけど、ブルーカラーは逆に増えるという流れなんでしょうか。
「そういう見方もあると思います。ただ、単純にAIができないからというより、現実的にロボット化や自動化がまだ難しいんですよ。ロボティクスの技術自体は進んでるけど、実際に現場に普及するには時間がかかる。特にコスト面が大きいですね。」
―― たしかに、現場での導入にはお金も時間もかかりますよね。
「そうなんです。だから、当面は人の手が中心にならざるを得ない。2030年までという区切りで見ると、まだまだ人の仕事が増える見立てになりますね。」
―― なるほど。2040年くらいになるとまた別の景色が見えそうですが。
「そうですね。僕らの話って、いつも2040年くらいを想定して話すことが多いですけど、今回のレポートは2030年までなので、スパンとしては短い。だからこそ、現実的に今の延長線上で増える仕事が上位に来ている感じだと思います。」
5位:店舗販売員
―― 5位は店舗販売員です。これも少し意外ですね。
「僕ね、この店舗販売員っていうのは、すごく未来を感じてるんですよ。」
―― どういう意味ですか。
「やっぱりAIで代替できることが増えていく中で、あえて人がやることに価値がある領域って残ると思うんですよ。たとえばブランドとかホスピタリティの部分です。」
―― ああ、たしかに。それはディズニーのような世界観にも通じますね。
「そうそう。ディズニーランドの清掃員とか販売員って、技術的には全部ロボットで代替できる。でも、あの世界では人がやっていること自体に価値がある。あれをロボットに置き換えたら夢が壊れるじゃないですか。笑」
―― たしかに。接客もブランド体験の一部になってますよね。
「そうなんです。だから、店舗販売員って単にモノを売る仕事じゃなくて、ブランド体験を提供する人になっていくと思う。お客さんが気持ちよく買い物できるようにする、その空気づくりとか関係性の部分がどんどん重要になる。」
―― つまり、AIが進化しても、人であることが価値になる。
「そう。あえて人が対応することがブランドの信頼につながる時代になると思います。だから、販売員は増えるというより、人を増やしてでもブランドを保つ方向に価値が出るんじゃないかなと。」
―― たとえば、高級ホテルとかラグジュアリーブランドもそうですよね。
「そうそう。効率化より体験価値を優先する。だから、同じ販売員という名前でも、より高度なホスピタリティを持つ職業として評価されると思います。」
AIリスキルの重要性
―― ここからはいよいよAIリスキル、学び直しの話ですね。
そうです。これが一番大事なところです。AIが進化していくと、どんな職種でもAIを使う力が必要になります。だからこそ、AIを前提としたリスキルが求められるんです。
―― リスキルといっても、AIの開発技術を学ぶという話ではないですよね。
そうですね。全員がエンジニアになれって話ではありません。大事なのは、自分の仕事をAIでどう拡張できるかを考えることです。たとえば営業なら顧客対応の自動化、マーケティングなら生成AIを使った分析やコピー作成とか。そういう実践の部分ですね。
―― なるほど。
AIは道具なので、どう使うかが価値になる。リスキルとは、AIを学ぶことではなく、AIを使って自分の価値をどう上げるかを考えることなんです。
OpenAIブループリントと社会の変化
―― 10月にOpenAIが発表した日本向けのブループリントの話も出ていましたね。
はい。経済ブループリントというもので、すごく象徴的な内容です。明治維新から高度経済成長まで、日本は常に技術革新を力に変えてきた。AIは次の繁栄をもたらす原動力になる、という話でした。
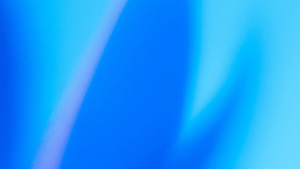
―― かなり前向きなメッセージでしたね。
そうなんです。独立分析の推計では、AIが日本のGDPを最大16%押し上げ、100兆円以上の経済価値を生む可能性があると記されています。
―― なるほど。
そしてブループリントでは三つの柱が掲げられています。包摂的なAIアクセス、戦略的インフラ投資、教育と生涯学習です。その中でも特に重要なのが“教育と生涯学習”です。
学び直しは避けられない
―― 企業側もAIスキルの習得を重視しているんですよね。
はい。世界経済フォーラムの調査では、企業の人材戦略としてアップスキリングを優先すると回答した割合が85%でした。一方で、スキルの陳腐化などを理由に人員削減を計画する企業も40%あります。
―― なるほど。
さらに、労働者100人のうち59人が2030年までに何らかの訓練を必要とすると見込まれています。内訳は、29人が現職のままアップスキル、19人が社内でリスキルと再配置、11人は必要だが訓練にアクセスできない、という構図です。
―― 実際、使えていない人と使える人の差は広がってますよね。
そうですね。たとえばパソコンを使うような仕事で、ChatGPTを使ったことがないという人がいたら、正直ちょっと不安になりますよね。一緒に仕事するのも難しい。
―― たしかに。
それに、単に使っているだけでは足りない。仕組みを理解していないと、間違った使い方をしてしまうこともあります。法人向けのクローズドなシステムの使い方をChatGPTに聞いてもうまくいかない場合がある。なぜなら、そういう情報は学習データに含まれていないからです。そういう理解がないと、正しく活用できない。
―― つまり、AIリスキルとはツール操作の話ではなく、仕組みの理解も含むんですね。
そう。AIがどう動いているのか、何が得意で何が苦手なのかを知っておく。そうすれば、使う場面を見極められるようになります。
対人スキルとAIスキルの両輪
―― ここまででAIスキルが必要という話がありましたが、他に意識すべきスキルはありますか。
AIスキルと並んで、対人スキルもすごく重要だと思います。たとえば共感力や交渉力、営業力。これは人と仕事をする上で根源的なスキルです。僕がさっき言った販売員の話もそうですけど、やっぱり人との関係を築く力はどんな時代でも必要だと思います。
―― AIに置き換えられない領域ですよね。
そうですね。折衝したり、根回ししたり、チームを動かしたり。AIが得意な最適化とは違う、人間ならではのスキルです。これがある人は、どんな業界に行っても強いと思います。
―― でも、対人が苦手な人もいますよね。
もちろんいます。だから、全員が対人スキルを極めろという話ではないです。苦手なら、尖らせ方を変えればいい。
専門性を尖らせるなら
―― たとえばどんな方向性があるんですか。
テクノロジーとかグリーン分野の新職種はこれからどんどん増えると思います。データ分析とか機械学習のスペシャリスト、サイバーセキュリティやフィンテックのエンジニア、環境や再生可能エネルギーに関わるグリーン分野の専門職とかですね。
―― なるほど。
フィンテックっていうのは金融とテクノロジーを掛け合わせた領域で、金融サービスをITで支える人たち。こういう分野は需要が高まっています。
グリーン分野も同じで、気候変動や環境対策に関わる技術職は増えていく。専門的なドメイン知識を持ってAIを活用できる人は、どの業界でも重宝されると思います。
―― 対人スキルが苦手なら、専門性を磨く方向に行くのもありですね。
そうです。ドメイン知識を徹底的に深めてAIを使いこなせれば、ハイパフォーマーになれます。
データを扱う力の重要性
―― スキルの中でもデータというキーワードがよく出てきますね。
そうですね。どんな職種にも共通して重要なのがデータを扱う力です。AIはデータがなければ動かないので、まずはどう集めて、どう使うかを考えることがリスキルの第一歩になります。
―― たとえばどんなイメージですか。
たとえばデザイナーでも、過去の案件データをAIに読み込ませて分析すると、自分の強みや傾向が見えたりしますよね。単価の高い案件の特徴とか、失注した案件の共通点とか。そういうのをAIに解析させると次に生かせる。
―― なるほど、職種を問わず応用できますね。
そう。データの扱い方が分かれば、どんな仕事にもAIを導入できます。自分の仕事に近いところから、データをどう見るか、どうAIに渡すかを考えるのがリスキルの始まりです。
学び方とリスキルの実践
―― 実際にどうやって学んでいけばいいんでしょう。
今は無料で学べる講座がたくさんあります。ChatGPT自体でも学べますし、AIをどう使うかを教えてくれる教材も増えています。まずは無料で試してみるのがいいと思います。
―― 継続するのが難しいという人も多いですよね。
そうですよね。だから、継続の仕組みを作るのが大事です。僕はパーソナルジムの話に似てると思ってて。ジムだって一人だと続かないけど、コーチにお金を払って通うと続く。リスキルも同じで、続けるために対価を払うのは全然アリだと思います。
―― なるほど。
ただ、無料でも十分できる環境があるので、まずは試してみて、続けられそうなら課金したり講座に通ったりすればいい。自分に合ったやり方を見つけるのが大事です。
―― 最後に一言お願いします。
僕のおすすめは、リスキルされる側じゃなくてリスキルする側に回ることです。学ぶだけじゃなく、教えられるようになると一番強い。僕らもそっちを目指して頑張りましょう。
