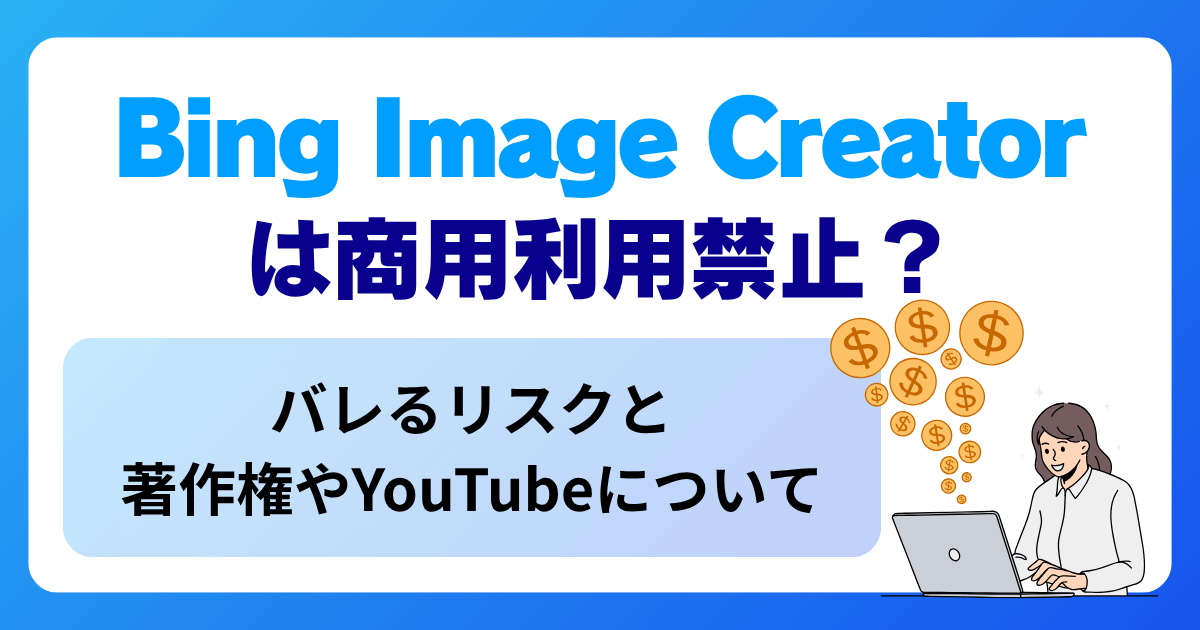
Bing Image Creatorは便利な画像生成ツールですが、商用利用がバレるリスクや著作権の扱いに注意が必要です。
特にYouTubeで利用する際は、規約違反や他者権利侵害を避けるため、生成画像の使用方法や開示の工夫が重要となります。
Bing Image Creatorは、特にMicrosoft Designerと混乱しやすいので、両者の利用規約を注意深く確認しなければなりません。
Bing Image CreatorとMicrosoft Designerの関係性
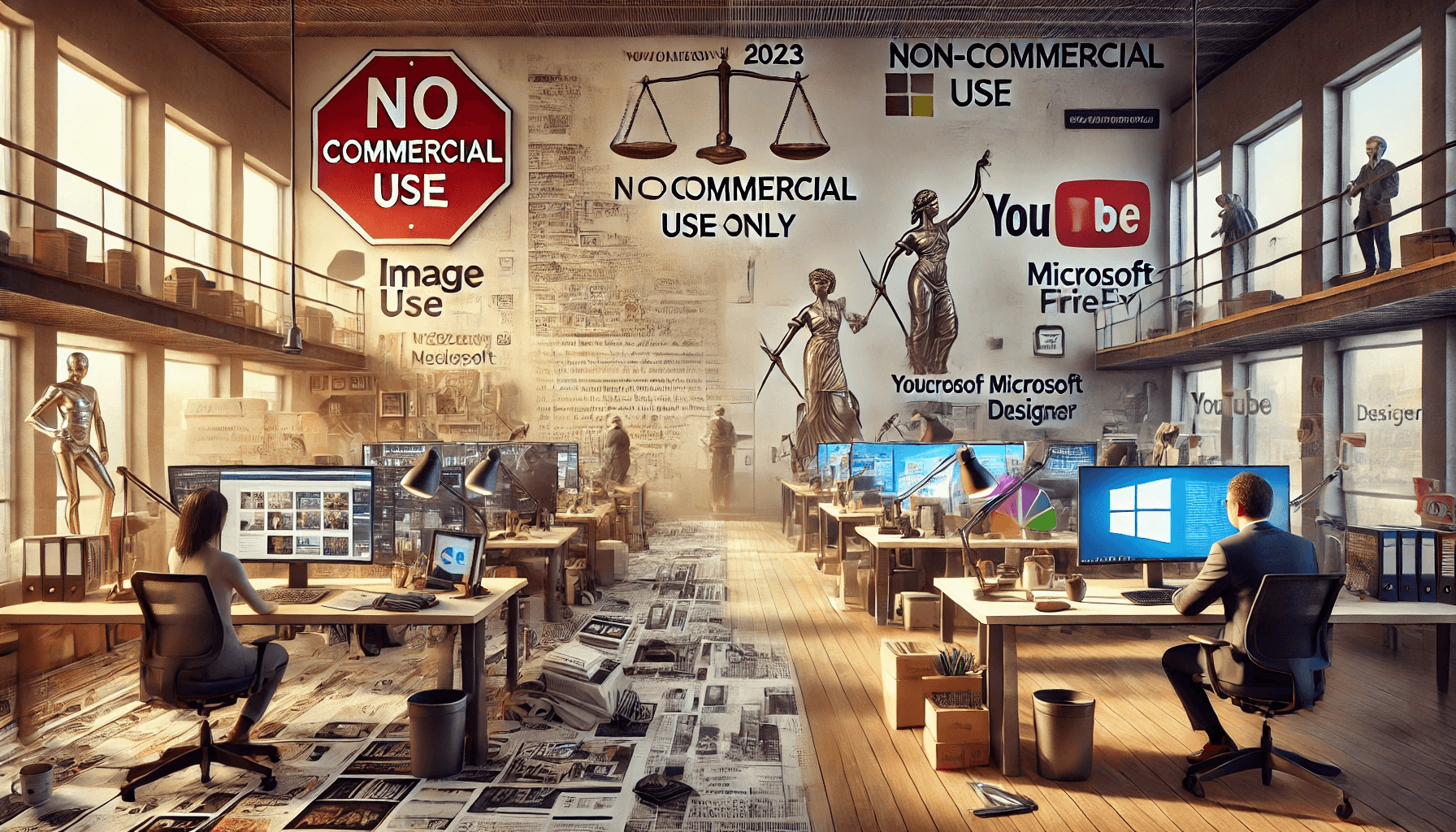
Bing Image CreatorとMicrosoft Designerは同じ生成エンジンを基盤としていますが、提供形態や利用規約が異なる画像生成サービスです。
両者の位置づけを理解することが、その後の商用利用可否や注意点を考えるうえで重要になるので、まず両者の関係を説明するところから始めます。
Bing Image Creatorとは?Microsoft Designerとの違い
Bing Image Creatorは、Bingの検索エンジン内で利用できる画像生成機能です。
ユーザーは検索と同じ感覚でプロンプトを入力し、AIによる画像を手軽に得ることができます。
一方、Microsoft Designerは、独立したデザインツールとして提供されており、多機能な編集やデザイン作成に組み込める点が特徴です。
両者は同じ画像生成エンジンを基盤にしていますが、別々のサービスとして運営されています。
そのため利用規約も別々のものが適用されるので、商用利用の可否や条件については、どちらのサービスを使うかによって注意が必要です。
過去の経緯:Bing Image CreatorとMicrosoft Designerの統合
2023年9月頃、MicrosoftはBingの画像生成機能(Bing Image Creator)とデザイン編集機能(Microsoft Designer)の連携を強化しました。
2024年1月には、Bing Image Creatorが「Image Creator from Designer」という名称に変更され、ブランドの再整理が行われる形でMicrosoft Designerの一機能という位置づけになりました。
しかし、現在は再び「Bing Image Creator」の名称が用いられており、Bing Image Creator・Microsoft Designerのどちらの入り口からでも画像生成機能を利用できる状態です。
このようにブランドやサービス名称の変更が繰り返されたことから、Bing Image CreatorとMicrosoft Designerのどちらの利用規約を確認すべきかが分かりにくくなり、商用利用を検討するユーザーの間で混乱が生じています。
Bing Image CreatorとMicrosoft Designerの商用利用に関する規約の違い
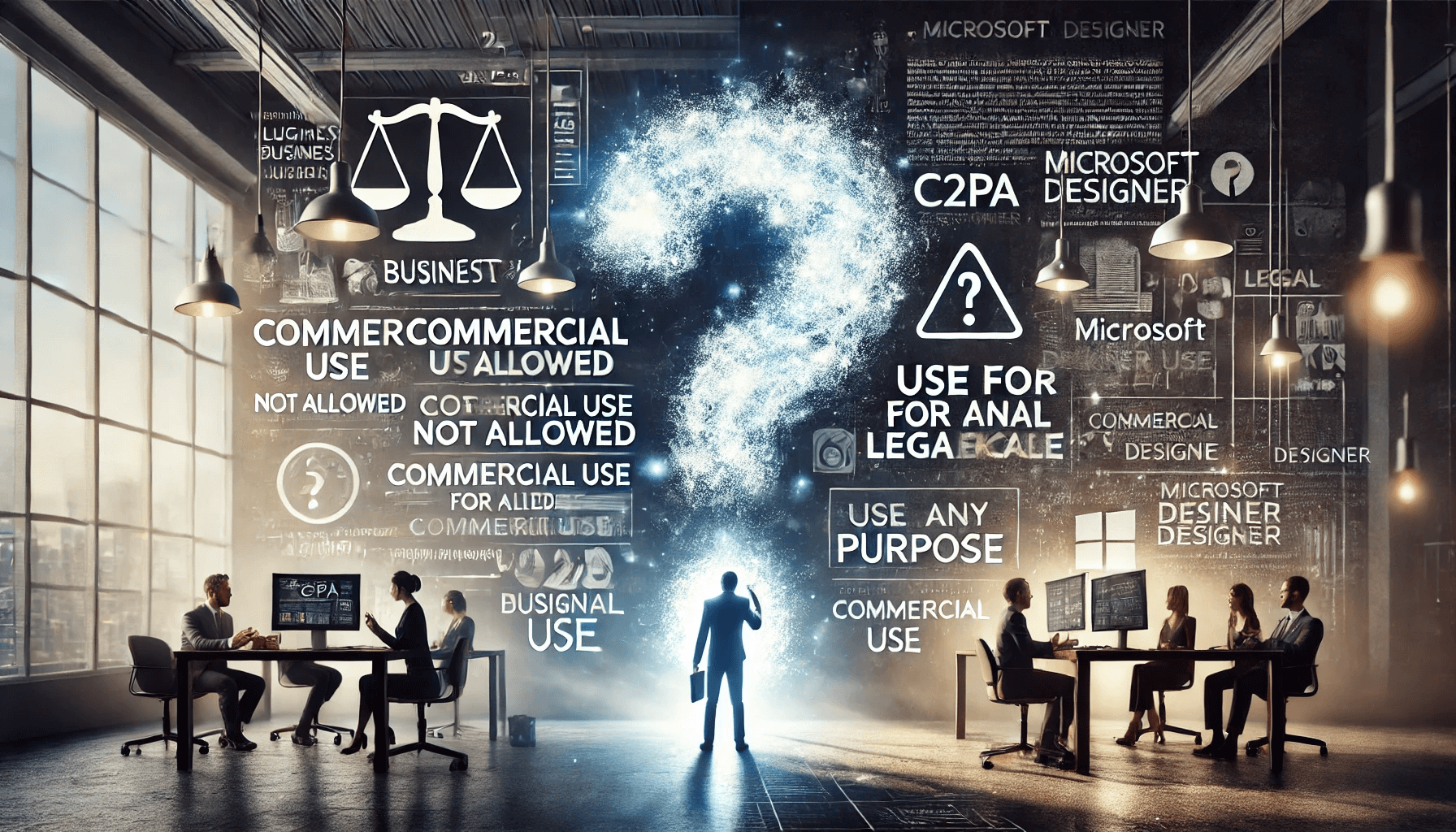
AI画像生成サービスを活用する際、見落としがちなのが「規約の違い」です。
Bing Image CreatorとMicrosoft Designerでは、商用利用の扱いに大きな差があります。
Bing Image Creatorの商用利用に関する規約
Bing Image Creatorの規約は、Bing Image Creator and Bing Video Creator Terms of Useで公開されています。
この規約では、商用利用について明示的に禁止する記載は見当たりません。
しかし一方で、積極的に許可する旨の記載もなく、利用範囲について明確に定義されていない部分があります。
そのため、商用利用を検討する場合には、解釈に幅が生じやすく、いわばグレーゾーンの状態となっています。
そのため、実際に商用で利用する場合は利用者が自己責任で判断せざるを得ないのが現状です。
また、将来的に規約が変更され、商用利用が制限される可能性も否定できません。
特に重要な商用プロジェクトでの利用は避けるのが安全であり、活用する場合はテスト用途や社内の内部検討資料といった限定的な範囲に留める使い方が無難です。
Microsoft Designerの商用利用に関する規約
一方、Microsoft Designerの規約には、以下に示すように「個人使用のみ」と明確に記載されています。
1.適用される使用条件。
(a) Designer (Image Generator とブランド キットの機能を含む) の使用は、これらの使用条件 (以下「本契約」といいます) ならびに Microsoft サービス規約に準拠するものとします。Microsoft サービス規約はここで言及されることにより本条件の一部となります。(b) お客様は、Designer の使用は個人使用のみとし、商取引の過程では使用しないことに同意するものとします。
そのため、商用利用ははっきりと禁止されており、企業や営利目的で利用することは規約違反にあたります。
違反が発覚した場合には、アカウント停止や法的リスクに発展する可能性もあります。
そのため、営利目的では一切使用せず、あくまで個人の趣味や学習目的の範囲に限定するのが適切です。
ビジネス利用を考えるユーザーは、他の商用利用可能な生成AIサービスを選択する必要があります。
Bing Image Creatorの商用利用が「バレる」意味:技術的仕組みや社会の反発
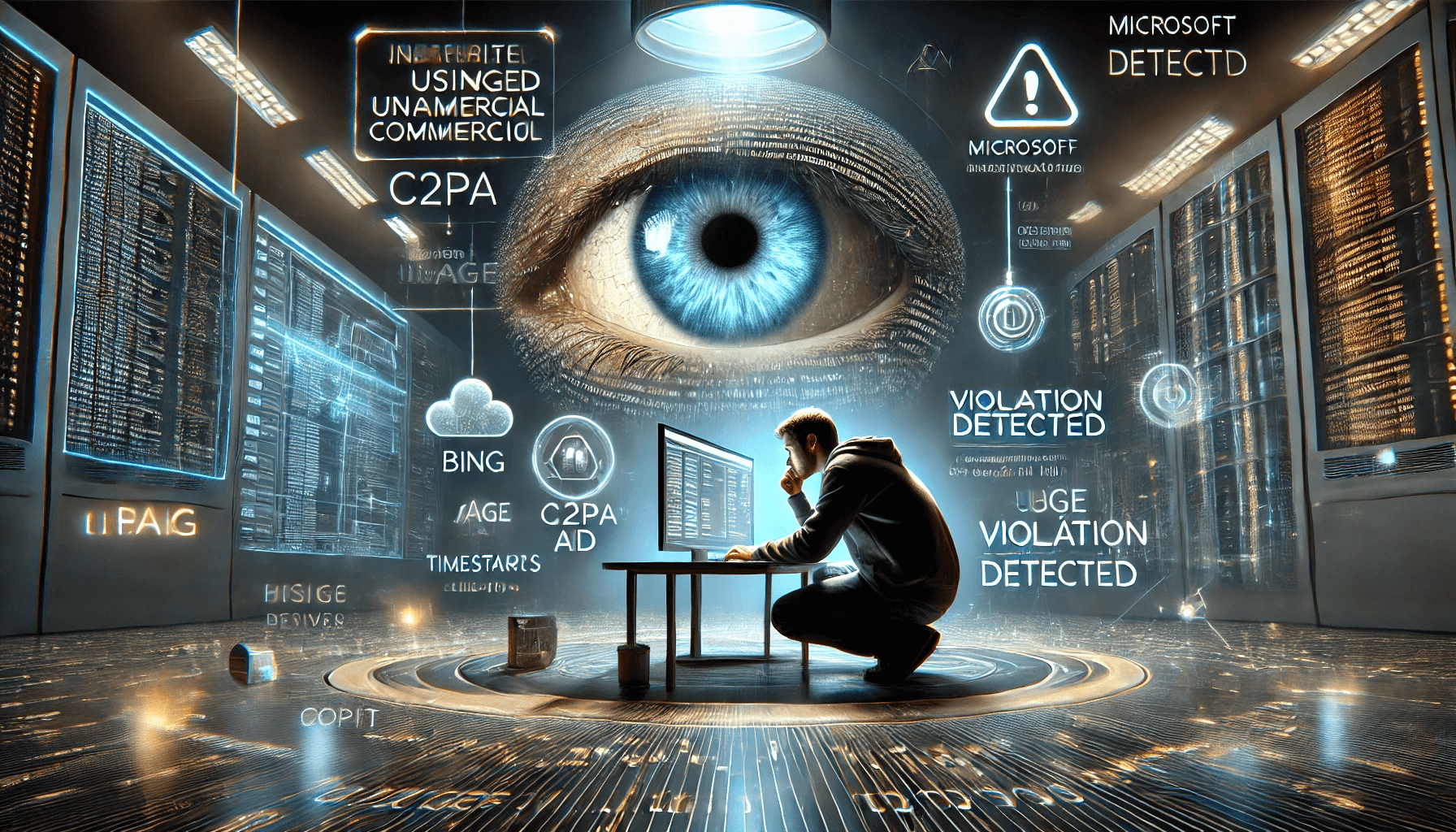
「Bing Image CreatorだろうがMicrosoft Designerだろうが、生成した画像は所詮同じAI生成画像では?」と考えるユーザーもいるかもしれません。
しかしAI生成画像には透かしやログが埋め込まれており、商用に利用した場合、その履歴は技術的に追跡可能です。
AI生成画像を利用する場合は、規約だけでなく世間の目にも気を付けなくてはなりません。
デジタル透かしについて
Microsoft は、Bing Image Creator や Designer による AI 生成画像には、すべて C2PA 規格準拠の Content Credentials(不可視デジタル透かし)を埋め込む仕様を導入しています。
この仕組みにより、生成日時・使用モデル・プラットフォームなどの情報がJPEGのメタデータとして保存され、後で解析可能になります。
しかも画像上には小さな「AI生成を示すアイコン」やロゴが含まれることがあり、視覚的にも「AIコンテンツである」ことが判別できる設計になっています。
ただしウェブサイトへのアップロード時にメタデータが消去されたり、スクリーンショットで加工すると透かしが消えるケースがあり、技術的にはまだ完全ではありません。
ログ解析の存在
AI画像生成に使用されたプロンプト・生成日時・アカウント ID・使用端末などは、すべてMicrosoftのサーバーにログとして記録されます。
したがって規約違反や利用目的の疑いが生じた場合、調査や通知、削除などの対応が可能です。
つまり透かしやメタデータだけでなく生成履歴全体が追跡可能であり、たとえば商用利用が禁止されている画像を商用利用していた場合、Microsoft 側で照合される可能性があります。
コミュニティの反発
問題が生じるのは、Microsoftの規約面や検出技術の能力に限られるわけではありません。
Bing Image CreatorのようなAI画像作成ツールを使用することで、時にはクリエイターコミュニティから強い批判を受けしまうこともあります。
たとえば、2025年6月に有名YouTuberのMrBeast(ジミー・ドナルドソン氏)が、AIを使ったYouTubeサムネイル生成ツール(注:Bing Image Creatorではない)を運用した事例があります。
THE TIMES OF INDIA、PC GAMER、tubefilterなどの報道によると、システムの運用開始後直ぐにクリエイターコミュニティから、これは「他人の作品を無断で模倣」するツールだと批判が殺到しました。
クリエイター仲間の間で、それぞれのブランドやサムネイルスタイルが無断で再現されたとして批判が強まり、「AI生成サムネによって創作者のクリエイティブが侵害されている」との声が広まったのです。
その結果、MrBeastはサービス開始からわずか数日で機能を削除・撤回するに至りました。
Bing Image Creatorの規約違反以前に、コミュニティの反発により商用利用がバレてサービス撤退・炎上につながる可能性もあるのです。
特にYouTubeなど、公の場で使用する際には、十分な配慮が必要です。
Bing Image Creatorの著作権・類似画像リスク
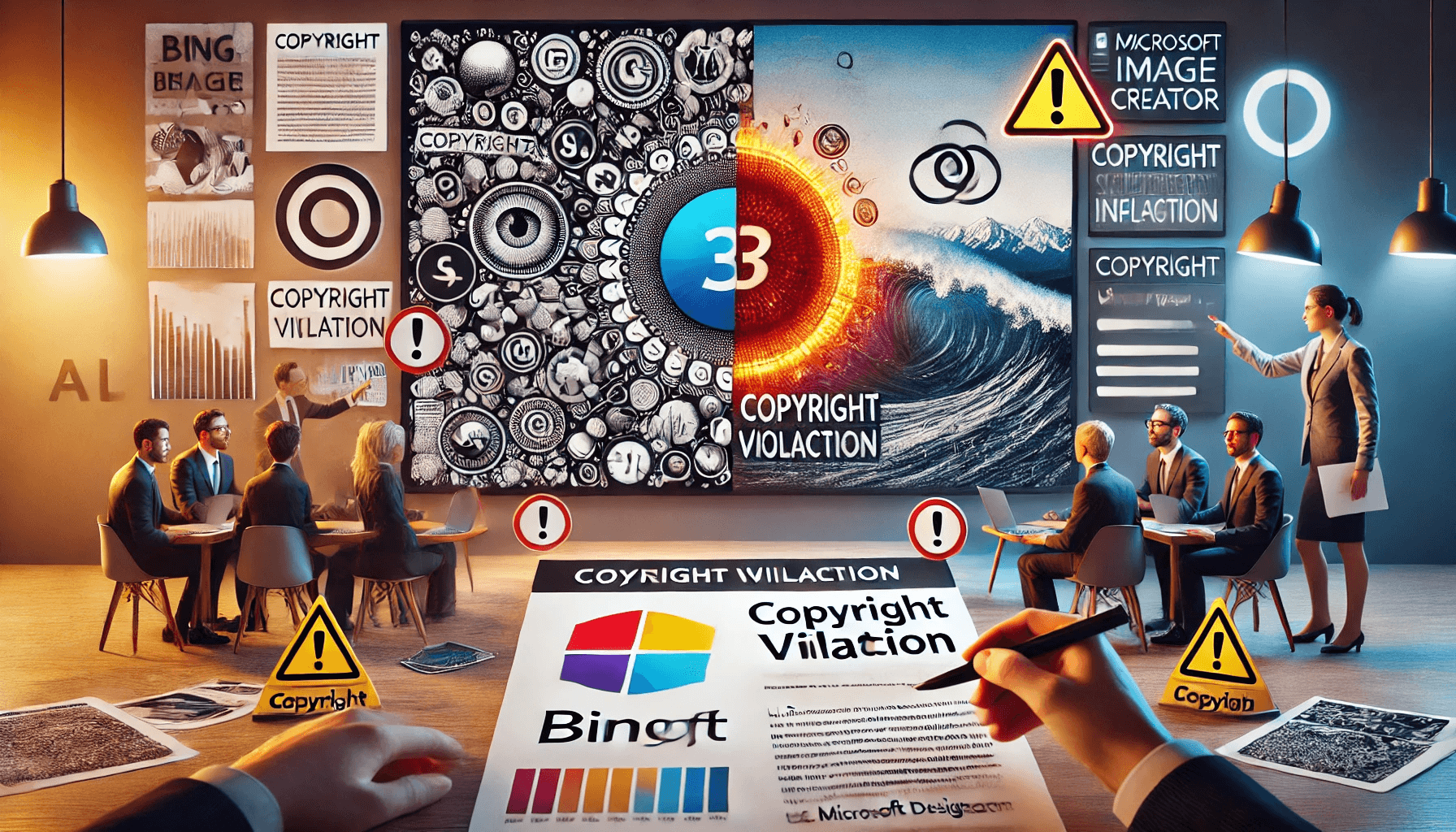
AI生成画像には著作権が認められないケースも多く、他作品との類似性や権利侵害に注意が必要です。
著作権法におけるAI 生成画像の扱い
日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したもの」が、著作物として保護対象になります。
ア 著作権法で保護される著作物の範囲
出典:AI と著作権に関する考え方について
○ 著作権法で保護される「著作物」について、法第2条第1項第1号では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されている。
文化庁の指針や法律学者の見解に基づくと、人間の創造的な関与がないまま、AIが自律的に生成した画像には、日本でも原則として著作権が認められないとされているのです。
重要なのは生成プロセスにおける「人による創作的寄与」です。
たとえば、プロンプトに含まれる表現が詳細かつ独自性に富んでいて、それにより生成された作品の表現に重大な影響を及ぼしていると判断される場合、その部分については著作権が認められる可能性があります。
文化庁の資料や法学研究では、画像生成AIに短い単語を投入しただけでは創作的寄与とは言えず、著作物性を認められにくい反面、詳細な指示文や選択・編集の過程が明確な場合には、著作性が認められる余地があるとされています。
AIが学習に用いた元著作物との「類似性」または「依拠性」が問題になるケースもあります。
生成された画像が既存作品と類似しており、単なる偶然ではなくAI利用者が意図的または結果的に模倣したと判断される場合には、著作権侵害となる可能性があります。
たとえプロンプトに明示していなくても、AIが学習した内容を反映して再現した場合には依拠性が認められると判断されることもあり、利用者は慎重な運用が求められます。
ただし、日本の著作権法では、AIの学習目的で既存著作物を利用することについて、一定の例外を認めています。
これはあくまで学習段階に限られ、生成物を使用する段階では、他の著作物との類似性の検討が必要です。
つまり日本の場合、AI生成画像に著作権が認められるには人間の「創作的寄与」が不可欠であり、単なる自動生成では著作物とみなされることは難しいというのが現状です。
ただし、詳細なプロンプトと編集を加えることで著作物性を主張できるケースもあるため、実務上は生成の記録や関与を可視化できる体制が求められます。
「ブランド名・キャラ名・企業ロゴ」のプロンプト記述は要注意
AIプロンプトに具体的なブランド名・キャラクター名・大企業のロゴなどを含めると、それに類似した画像が生成されるリスクがあります。
これにより、著作権侵害や商標権・肖像権の問題に発展する可能性が高まります。
たとえば、Nintendoのマリオに関する研究では、「videogame, plumber」といった抽象的なキーワードだけで Mario に類似した画像が生成された例が報告されています。
We show that state-of-the-art image and video generation models can still generate characters even if characters’ names are not explicitly mentioned, sometimes with only two generic keywords (e.g., prompting with “videogame, plumber” consistently generates Nintendo’s Mario character).
和訳:最先端の画像・動画生成モデルは、キャラクターの名前が明示的に言及されていなくても、時には2つの一般的なキーワードのみで(例えば、「videogame, plumber」というプロンプトでNintendoのマリオキャラクターが一貫して生成される)、引き続きキャラクターを生成できることを示しています。
出典:Cornell University
こうした実例は「具体名」「固有名詞」「象徴的ロゴ」などを含む文言が、AIにとって模倣しやすいプロンプトとなり得るため、避けるべきであることを示しています。
生成した画像が他者の権利を侵害するリスクを高めるからです。
安全なプロンプト設計と後処理による安全性向上
AI生成画像を安全に使うためには、まずプロンプトの工夫と生成後の編集処理が重要です。
プロンプトを設計するときは、ブランド名・キャラクター名・特定のロゴなど具体的な固有名詞を避け、スタイル・色調・構図など抽象的な表現にとどめることで、他者の著作物と近づき過ぎるリスクを抑える効果があります。
このような汎用的な記述を使うことで、生成された画像が既存の著作物に依存していると判断される可能性を低くできます。
生成された画像をそのまま使うのではなく、必ず後処理として加工や編集を加えることも推奨されます。
画像編集ソフトを用いてテキストやグラフィック要素を付け加え、視覚的にも人の創造性が反映されている状態に仕上げることで、著作権上「人の著作物」として認められる可能性が高くなります。
AI生成部分と区別できるように編集を施すことが、安全性向上に直結します。
最近の研究では、工夫次第でAIが学習済みの既存作品と似た画像を生成するリスクを大幅に減少させられることが示されています。
プロンプトに思考過程を記述させる(Chain-of-Thought プロンプト)などの特殊なテクニックを使うのです。
特に、ネガティブプロンプト(特定要素を除外する指示)と組み合わせた転写抑制の手法は、利用者の意図次第で侵害リスクを半分以上低減できるという実証もあります。
こうした実務的な対策を踏まえて、生成時と使用時の両段階で「人の創意・工夫が介在している状態」を意識することで、AI生成素材を商用でも安心して活用することが可能になります。
Bing Image CreatorをYouTubeで利用する際のポリシー
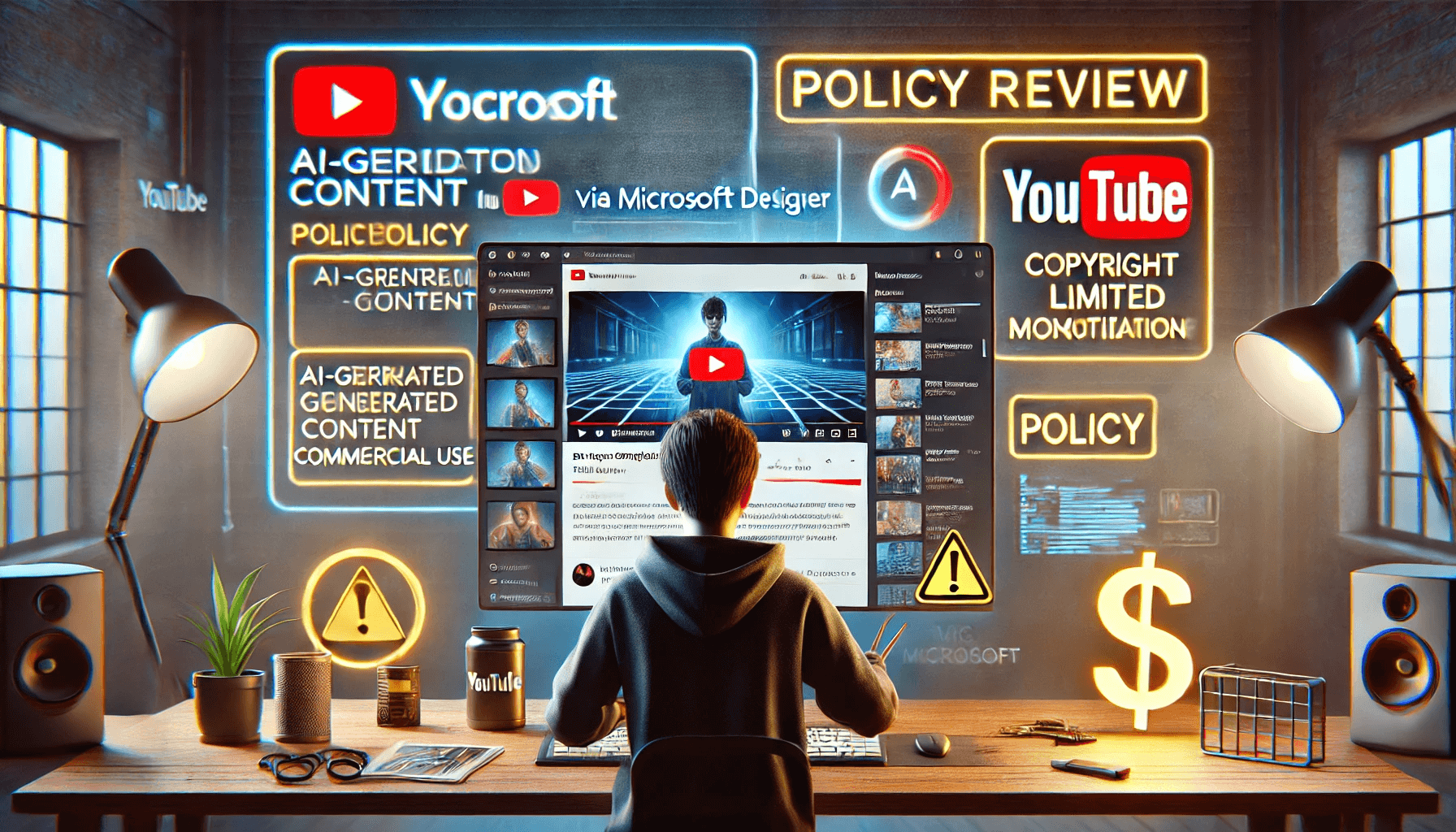
YouTubeでBing Image Creatorなどで生成したAI画像の使用することは禁止されている訳ではありません。
しかし、誤認・侵害表現には慎重になってください。
利用する際には、収益停止や削除リスクを避ける工夫が求められます。
YouTubeのAI処理方針
YouTubeはAI生成技術の使用自体を禁止してはいません。
しかし視聴者を誤認させる虚偽表現や重大な著作権侵害が伴うサムネイルや動画に対しては、コミュニティガイドラインや広告向けコンテンツポリシーにより、削除や収益化停止の措置をとることがあります。
特に、AIによって大量生産されただけで人間の創意がほとんど介在ない動画は、YouTube Partner Programのポリシーに抵触し、「認められない非オリジナル作品」とみなされる可能性が高まっています。
2025年7月15日に施行された最新の改定では、これらの「量産型」や「反復的」な動画に対して広告収益が制限されるなど、より厳格な運用が明確化されました。
What we check when we review your channel
If you’re making money on YouTube, your content should be original and “authentic.” This means that we expect your content to:
- Be your original creation. If you borrow content from someone else, you need to change it significantly to make it your own.
- Not be mass-produced or repetitive. It should be made for the enjoyment or education of viewers, rather than for the sole purpose of getting views.
和訳:チャンネルを審査する際に確認する内容
YouTubeで収益を得るには、コンテンツがオリジナルで「本物」である必要があります。つまり、コンテンツには以下の要件が求められます。
- 自分だけのオリジナル作品を作りましょう。他者からコンテンツを借りる場合は、自分の作品にするために大幅に変更を加える必要があります。
- 大量生産や繰り返しのコンテンツは避けてください。視聴回数を増やすことだけを目的とせず、視聴者の楽しみや教育のために制作されるべきです。
クレジット表記・説明欄での申告
「AI生成/Copilot使用」「アセット出典」など、明示により問題発現時の透明性を確保することが可能です。
すなわちYouTubeでAI生成画像を使用する場合には、動画説明欄に「AI-generated image via Microsoft Designer」等と明記し、「YouTube公式の開示機能(Altered content設定)で AI 使用を開示することが推奨されます。
We require that creators disclose when realistic content is made with altered or synthetic media, including Gen AI Labels may then appear within the video description information, and if content is related to sensitive topics like health, news, elections, or finance, we may also display a label on the video itself.
和訳:クリエイターは、リアルなコンテンツがGen AIなどの改変または合成メディアを使用して作成されている場合、その旨を明らかにする必要があります。その場合、動画の説明情報内にラベルが表示されることがあります。また、コンテンツが健康、ニュース、選挙、金融などのデリケートなトピックに関連している場合は、動画自体にラベルが表示されることもあります。
出典:How YouTube is Approaching AI Responsibly
視聴者や YouTube に対して使用意図や生成元を明らかにすることで、後にトラブルが起きた際に、削除や収益停止のリスクを軽減する効果があります。
サムネイルなし設計や商用利用OKの画像を併用する代替フロー
YouTube チャンネル運用の観点からは、AI生成画像を使わない方法との併用や、サムネイル設計から排除する設計も検討すべき代替策です。
ある程度以上の安全策を求めるなら、AI生成画像ではなく、人の創作性が明確に反映できる手段を併用することも重要です。
完全に人が設計・作成したサムネイルや、商用利用が明確に許可されているツールで生成された画像を使用することで、YouTube ポリシーとの整合性および法務リスクを大きく下げられます。
こうした運用設計は、AI生成に依存するだけでは不安なクリエイターや企業にとって、安全性の高い代替手段だといえます。
安全に商用利用したいならAdobe Fireflyが最適
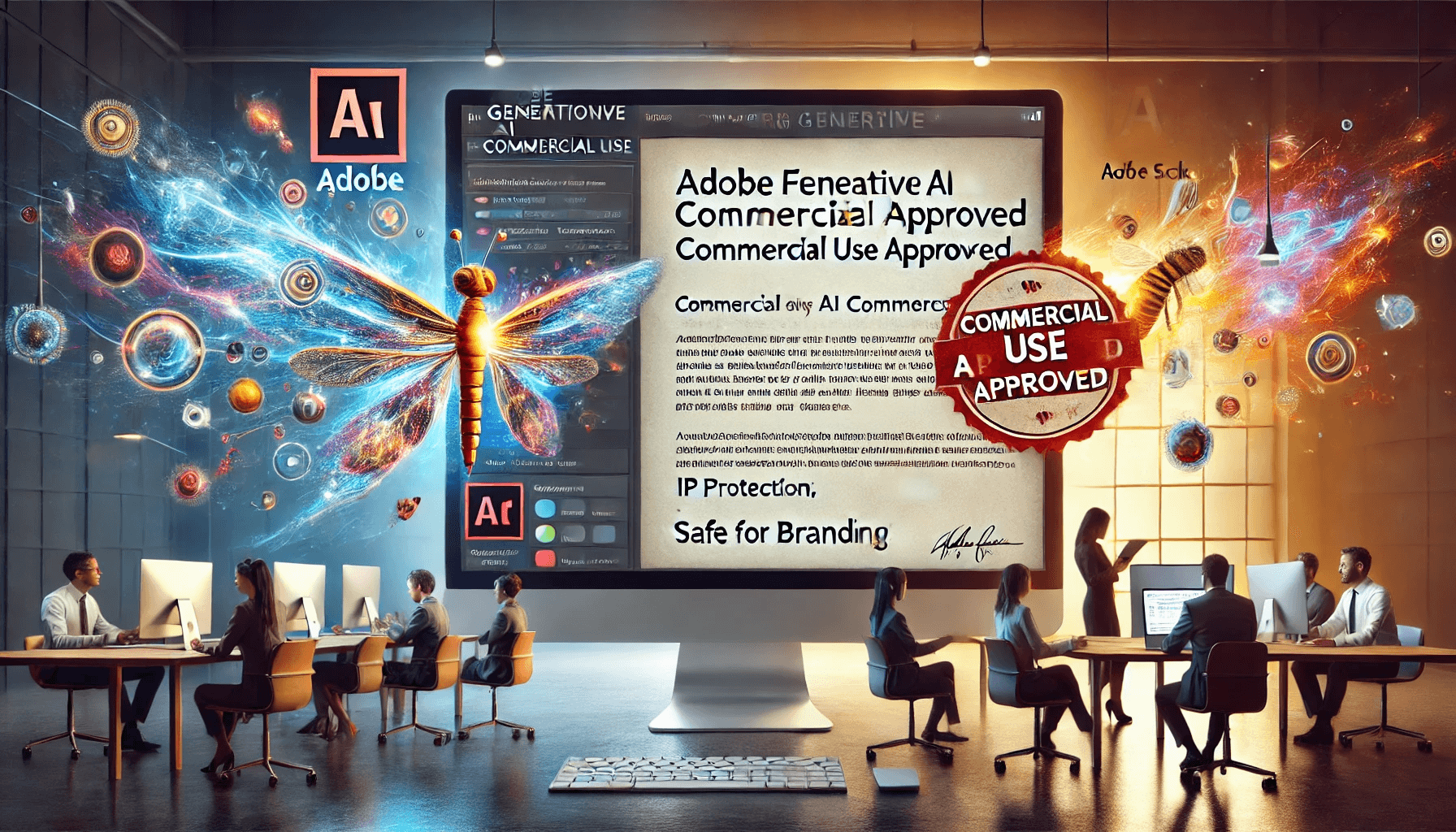
商用利用を公式に認め、法的補償も整備されたAdobe Fireflyは、安心して使える生成AIツールの代表格です。
Adobe Fireflyのライセンス・ガイドラインで「商用利用可」を明示
Adobe Fireflyは、生成AIの商用活用を安心して行いたい方にとって非常に頼もしいツールです。
まず注目すべき点は、Adobeが明示的に「商用利用を認める」立場を採っている点です。
公式の Generative AI User Guidelines(2025年4月改訂版) によれば、ベータ版で「商用不可」と明示されている場合を除き、Fireflyで生成された画像や動画は一般的に商用プロジェクトへ使用可能とされています。
また、Adobeのフォーラムでも「ほとんどすべての商用向けプロンプト生成が許可されている」と共有されており、商用利用に関する公式の姿勢が明確です。
さらに、FireflyはAdobe Stockを含むライセンス済み画像やパブリックドメイン素材のみを使用してトレーニングされているため、無断転載や著作権侵害のリスクを最小化しています。
Adobe社のCTO・Ely Greenfield氏は、商用安全性が Fireflyを選ぶ最大の理由であると明言し、Firefly のモデルが他者の権利を侵害する可能性を防ぐ目的で設計されていると述べています。
“We still have lots and lots of customers for whom taking stuff to production, they will only use Firefly because the commercial safety really matters to them,” Ely Greenfield, Adobe’s chief technology officer for digital media, told Reuters in an interview on Monday.
和訳:「実際に制作に使う用途では、Firefly を選ぶお客様も非常に多くおられます。彼らにとって重要なのは、商用として安全に利用できるかどうかだからです。」Adobe デジタルメディア部門 CTOであるEly Greenfield氏は、月曜日のロイターのインタビューに対してこのように語った。
出典:Reuters|Adobe adds AI models from OpenAI, Google to its Firefly app
法的補償条項や利用条件も開示済
Adobe Fireflyの場合、ベータ版では制限を受けるケースがありますが、正式版では商用補償や契約の安定性が提供されており、安心して長期利用できます。
また、Adobeはライセンス面での補償についても明記しています。
生成物が第三者の知的財産権を侵害したとされる場合、Adobe StockのIP補償規定に準じて、ユーザーを守る制度が設けられています。
これは、特に商用利用時の法的リスクを考える企業やクリエイターにとって、心強い支援策となります。

ただし、注意点として、Adobe Firefly の ベータ機能は商用禁止となっているケースがある点は見落とせません。
必ず各機能のステータスを確認することが重要です。
シンプルな運用フロー
Adobe Fireflyを採用する場合、生成履歴や出力クレジット表示の保存、社内承認プロセスを導入しましょう。
法務的に説明可能な運用体制を整えることでリスクを最小化できます。
実務での運用においては、以下のようなシンプルなフローを推奨します。
まず無料トライアルでAdobe Fireflyを試し、社内レビューによって内容とクレジット表示を確認します。
その後、必要に応じて Firefly ProやCreative Cloud Proにアップグレードすることで、継続的・安定的な商用利用環境を整備できます。
プロンプトや生成履歴、出力クレジット表示の記録を保存することで、法務チェックや透明性の説明材料として活用できてリスクマネジメント上も効果的です。
\ 無料プランから利用可能 /
まとめ
Bing Image Creatorは、商用利用について明確な禁止は記載されていない一方で、Microsoft Designerは個人利用のみと規約で明示されています。
そのため商用利用を検討する場合はBing Image Creatorを使う選択肢が考えられますが、権利侵害や規約変更リスクを配慮して、慎重に利用しなければなりません。
用途に応じた安全な運用や、Adobe Fireflyなどの商用利用可能なツールの併用も検討すべきです。
