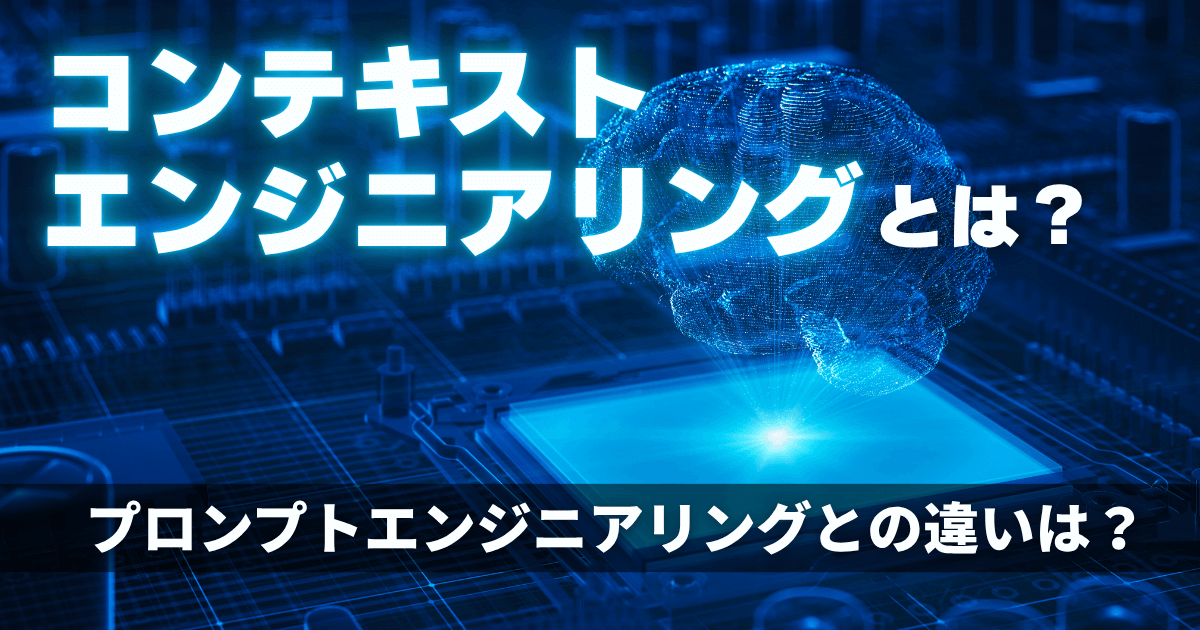
コンテキストエンジニアリングとプロンプトエンジニリングの違いをご存知でしょうか?
実は生成AIの精度や一貫性を本質的に高めるには、「コンテキストエンジニアリング」という情報設計の視点が不可欠なのです。
本記事では、コンテキストエンジニアリングとは何か、プロンプトエンジニアリングとの違い、RAG連携やナレッジ活用などの実践手法まで具体的に解説します。
コンテキストエンジニアリングとは何か?
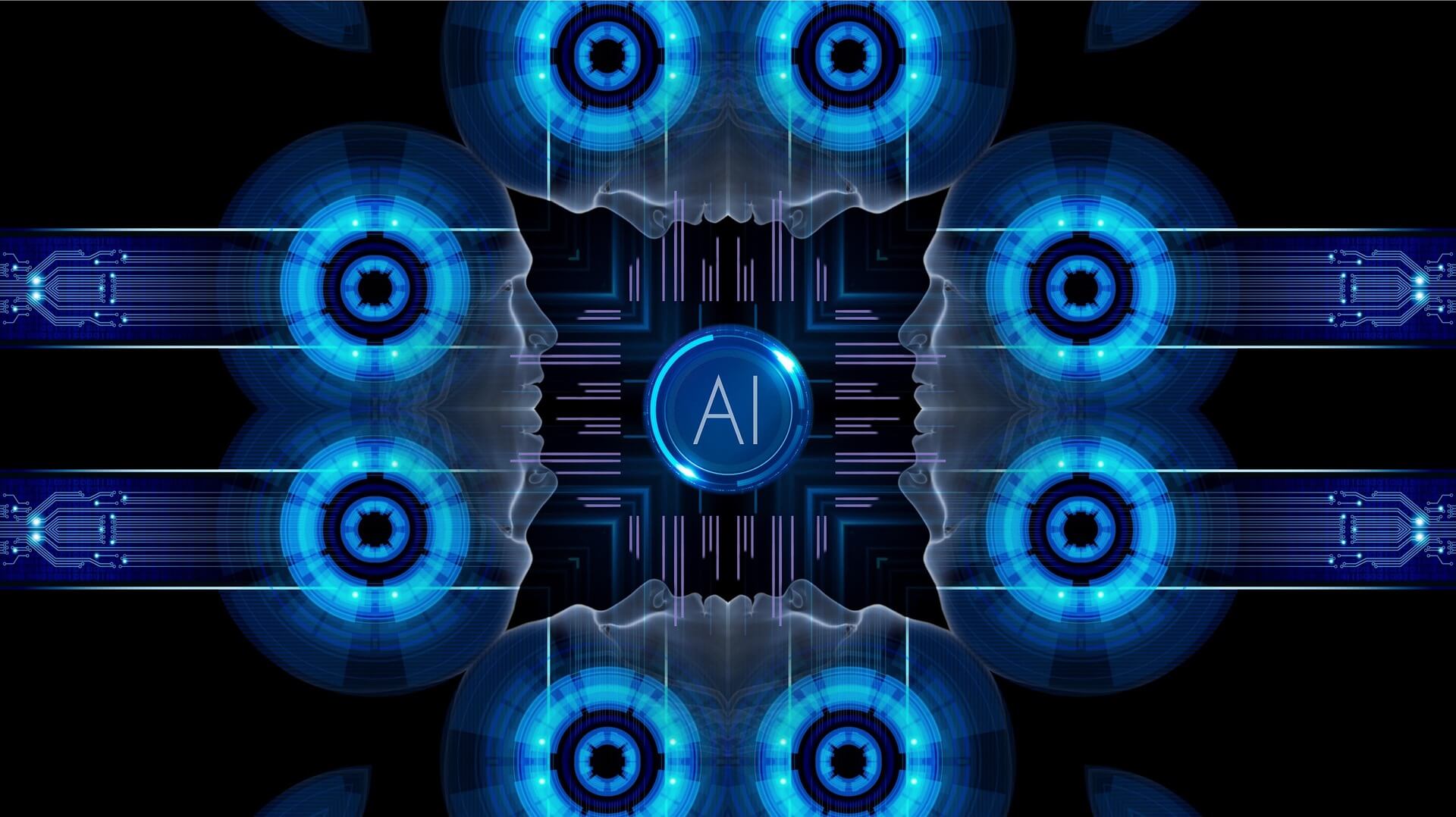
コンテキストエンジニアリングとは、一体何なのか?
生成AIの性能は、モデル自体の賢さだけでなく、どんな情報を・どの順番で・どう渡すかによって大きく変わってきます。
以下では、その基本的な概念と重要性について詳しく解説していきます。
コンテキストエンジニアリングの定義と役割
「単なるプロンプト調整ではなく、情報を適切な形と順序で与える情報設計」
LLMの「短期記憶」に限りがある中で、精度ある出力をするために情報の選別・整理を行うこと
多くのAIの誤作動はモデルの能力不足ではなく、誤った文脈設計によるものが原因であることが多いです。
そのため、AI活用において、コンテキストエンジニアリングは重要な鍵を握る役割を持っているといえます。
AIにおける「コンテキスト」の意味を理解する
AIにとっての「コンテキスト」とは、応答の前に与えられるすべての情報を指します。
単なるプロンプトだけでなく、ルール(システム指示)・会話履歴・外部データ・使用するツールなども含まれるのです。
たとえば、誰かに「旅行の手配をして」とだけ伝えると国内か海外か、予算や日程も分からず戸惑いますが、「3万円で週末に温泉地へ」と伝えれば具体的な判断ができます。
AIも同じでプロンプトだけでなく、ルールや履歴、外部データ、使用ツールを含む文脈が必要なのです。
それらを最適に整えるのが、コンテキストエンジニアリングの役割です。
生成AI活用のカギとして注目される理由
コンテキストエンジニアリングは、モデルの精度そのものではなく、「入力設計が出力成果を左右するのではないか」という疑問が出てきたことで注目されるようになりました。
そのため、生成AIを上手く活用していくにはモデルの性能そのものよりも「どのような情報を、どのように入力するか」が重要になってきたのです。
特に、コンテキストエンジニアリングは、出力結果の一貫性向上、入力コストの削減、パーソナライズ対応といった観点から、生成AI活用の成否を分ける重要な要素となっています。
こうした文脈設計を支える技術が、生成AIの実用性を高めるカギであるといえるのです。
プロンプトエンジニアリングとの違いを比較する

生成AIの活用が進む中で、「プロンプトエンジニアリング」と並んで注目されているのが「コンテキストエンジニアリング」です。
どちらもAIの出力品質に大きく関わる技術ですが、目的や設計の視点には明確な違いがあります。
ここでは、両者の役割や適した用途をわかりやすく整理します。
プロンプトエンジニアリングの目的と特徴
プロンプトエンジニアリングは、AIの性能を最大限に引き出すための重要な設計技術です。
タスクに応じて適切な指示を与えることで、出力の精度を高めたり、幻覚や誤動作を防いだりする役割を担います。
ここでは、その具体的な目的と特徴について整理します。
プロンプトエンジニアリングの主な目的は、LLM(大規模言語モデル)の性能を最大限に引き出すことです。
AIに適切なタスク指示を与えることで精度の高い応答を得られるようになり、不適切な出力(hallucination)を防ぎます。
また、敵対的プロンプトへの対策や安全性の確保も重要な目的の一つとなっています。
これらの取り組みにより、作業効率や再現性の向上を図ることができます。
プロンプトエンジニアリングは、自然言語でAIに命令を与える設計技術として特徴づけられます。
単純な質問ではなく、構造化された文脈を含むプロンプトを重視し、タスクに応じてプロンプト形式を柔軟に調整することが求められます。
モデル訓練においてはfew-shotやzero-shotなどの手法にも応用可能で、試行錯誤によりプロンプトを最適化するプロセスが重要です。
コンテキストエンジニアリングは“環境設計”の技術
コンテキストエンジニアリングとは、AIが最適に理解・応答できるよう情報の順序や構造を設計する技術です。
プロンプトエンジニアリングが「どんな指示を出すか」に焦点を当てるのに対し、コンテキストエンジニアリングはその指示が効果を発揮する“土台”をつくる役割であるといえます。
例えるのなら、プロンプトはレシピの「調理手順」、コンテキストは「食材の準備」や「キッチンの整理」であるといえます。
準備が整っていてこそ、レシピどおりに美味しく仕上がるのです。
両者の違いをわかりやすく表で解説
プロンプトエンジニアリングとコンテキストエンジニアリングは、どちらも生成AIの性能を引き出すうえで重要ですが、関心の対象や用途、設計の範囲は大きく異なります。
ここでは両者の違いを「目的」「操作対象」「失敗例」などの観点から整理し、役割や使い分けを理解しやすくするために表形式で比較して紹介します。
| 観点 | プロンプトエンジニアリング | コンテキストエンジニアリング |
|---|---|---|
| 実行する意図 | 単発の命令文(プロンプト)の表現を工夫 | AIに見せる情報全体の構成を設計すること |
| ゴール | 1回の入力で狙った応答を得る | 一貫性のある回答を継続的に引き出す |
| 操作対象 | 入力欄に直接入力するテキスト | 会話履歴・外部データ・設定など複数の情報要素 |
| 向いている用途 | SNS投稿、広告コピーなどの単発タスク | 顧客サポート、AIエージェント、複数ターンの対話 |
| ありがちな失敗例 | 表現不足で意図が伝わらず、的外れな回答が返ってくる | 情報が過多または整理されておらず、目的に沿わない出力になる |
| 位置付け | コンテキストの一部として機能する要素 | プロンプトも含めた文脈全体を設計する枠組み |
コンテキストエンジニアリングの構成要素

AI活用におけるコンテキストエンジニアリングの重要な要素とは何なのか?
鍵となる要素は「書き込み」「選択」「圧縮」「分離」の4つの戦略です。
これらは、優れたAIシステムを設計・構築するための基本的な要素であるといえます。
書き込み(Write)で情報を永続化
書き込みとは、AIが必要に応じて参照できるように、コンテキストウィンドウの外に情報を準備・保存しておくことを指します。
具体的には、「システムプロンプト」によって、AIの役割や出力の形式をあらかじめ明示(たとえば「あなたは法律専門家として対応してください」といった指示)したり、「メモ保存」のように、タスク遂行中の思考や中間ステップを外部に記録することで、文脈の継続性を維持できます。
「Few-shot learning」を使って、入力と出力のサンプルを提示することで、AIに期待する応答のスタイルや基準を具体的に示すことも可能です。
これらの工夫は、あたかもAIに“後で見返せるメモ”を渡しておくようなもので、特に複雑なタスクの精度を高めるうえで有効です。
選択(Select)で適切な情報を取り出す
選択とは、AIに与える情報の中から本当に必要な要素だけを抽出し、不要なノイズを取り除くためのプロセスです。
RAG(検索拡張生成)を使えば、ユーザーの意図に沿った情報を意味ベースで抽出し、関連性の高い文書だけをAIに渡すことができます。
また、情報を関連性や新しさといった基準で優先順位づけすることで、古いデータに惑わされず、必要なコンテキストをより的確に伝えることもできます。
圧縮(Compress)でトークン制限に対応
コンテキストウィンドウにはトークン数の上限があるため、情報を効率よく圧縮することが欠かせません。
まず基本となるのは、会話履歴や長文の文書を簡潔にまとめる「要約」です。
自動要約機能を活用すれば、冗長な部分を削減し、必要な情報だけを残すことができます。さらに、「再帰的要約」によって、その要約をさらに短縮することで、限られたスペースを最大限に活用できます。
「プルーニング」という手法では、文脈と関係の薄い情報や重複した内容を取り除き、精度と効率の両方を高めることができます。
こうした圧縮の工夫は、情報過多による誤解や出力精度の低下を防ぐために重要です。
分離(Isolate)で情報の衝突を防止
分離とは、複数の情報が干渉し合わないように整理し、文脈の混乱を防ぐための技術です。
たとえば「モジュール化」によって、各エージェントや処理機能ごとに専用のコンテキストを設けることで、役割ごとの情報が明確になります。また、「記憶の分類」を行うことで、直近の会話内容とユーザーの長期的な好みや履歴とを分けて管理でき、意図の取り違いを防げます。
さらに、「ツールの使い分け」によって、タスクの種類に応じた適切なツールのみを使用させることで、AIの誤操作を避けることも可能です。
これらの工夫は引き出しを用途別に整理するように、情報を適切に仕分けることでAIの精度と応答の安定性を高めることを可能にします。
コンテキスト設計のよくある失敗

コンテキストエンジニアリングはAIを活用する上で効果的な手法ですが、設計ミスが原因でAIの出力精度が大きく下がることがあります。
ここでは、よくある3つの失敗例を解説します。
情報量が多すぎてAIが混乱してしまうケース
大規模言語モデルには、処理できるトークン数に限界がある「コンテキストウィンドウ」が存在します。
あれこれ情報を詰め込みすぎると、重要な指示が後方に押しやられ、モデルが参照できない範囲に追い出されることがあります。
たとえば、FAQや前回の会話ログ、JSON形式の指示、社内資料などをすべて一括で送信し、最も重要な「今回の指示」を末尾に置いてしまった場合などです。
このような状態では、どれほどプロンプトの工夫を凝らしても、AIは指示自体を正しく認識できない可能性があります。
情報の順序・構造が整理されていないケース
モデルは「文脈内のすべての情報を均等に理解する」わけではありません。
構造化されていない箇条書きや、体裁の乱れたテキストが含まれると、内容の重要度や関係性を見誤りやすくなります。
たとえば「過去の会話ログ」をそのままプレーンテキストで貼り付けると、文脈の流れがつかめず、意図と異なる解釈が行われることがあります。
こうした設計ミスは、特にRAGや長期メモリを活用する場面で誤動作の原因となりやすいため、注意が必要です。
「目的」が不明確で意図した出力にならないケース
一見するとプロンプトや構成が丁寧に設計されていても、モデルが「この会話の目的は何か?」を正しく把握していないと、返答がぶれたり的外れな応答になってしまうことがあります。
たとえば、前提情報が十分でも「最終的に何を求めているのか」が曖昧な場合、出力は漠然とした内容になりやすくなります。
これは単なるプロンプトの文言ミスではなく、「全体的なコンテキスト設計」の問題に起因します。
このように、プロンプトだけではカバーできない課題がコンテキスト設計の甘さとして現れるのです。
コンテキストエンジニアリングの実践方法
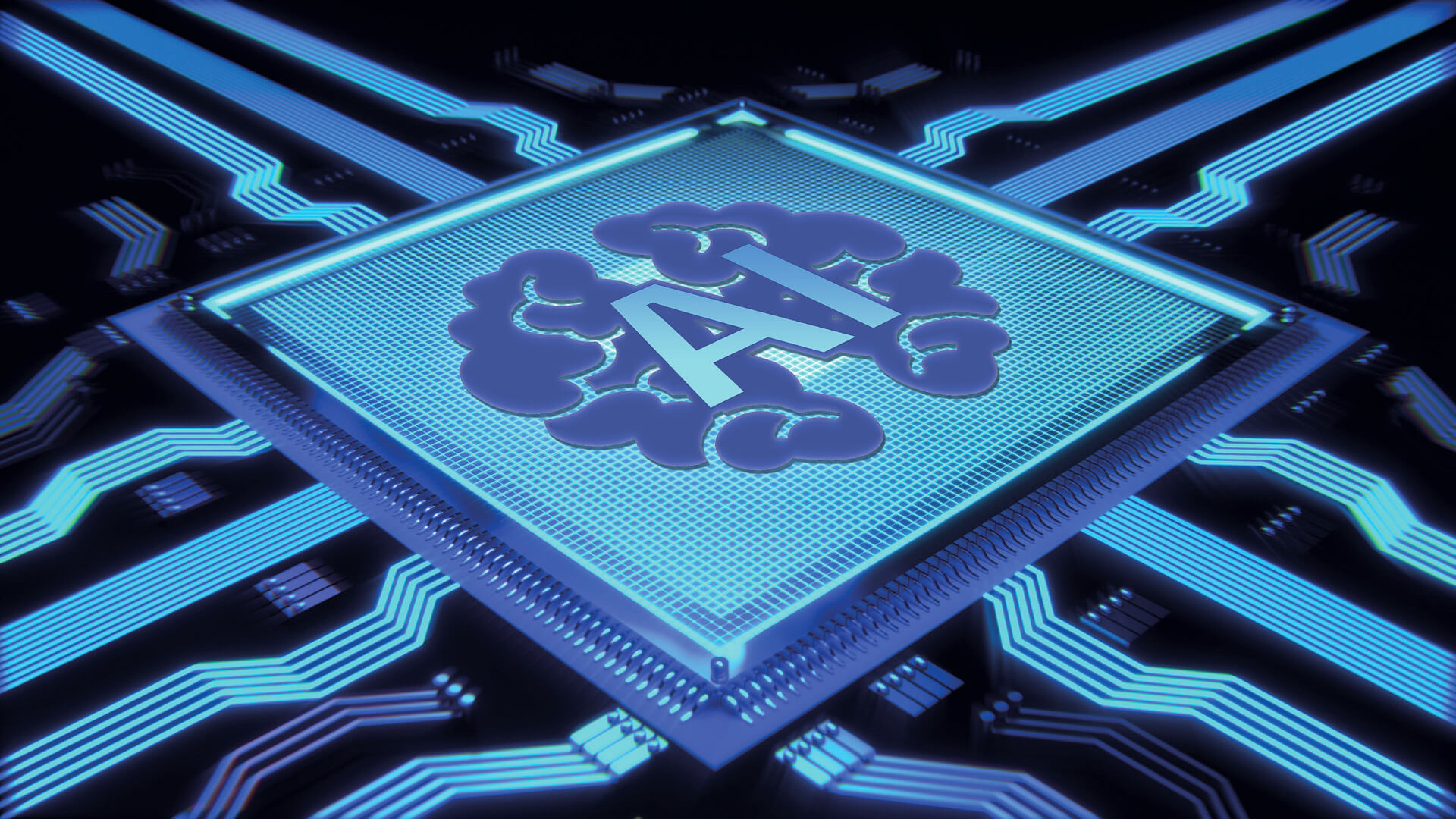
AIを活用する際は、ちょっとした工夫を加えるだけで、出力の精度や一貫性が大きく変わります。
ここでは、特別なツール不要で実践できる具体的な方法を4つ紹介します。
冒頭で「目的」と「前提条件」を明示する
ChatGPTを使う際には、冒頭で「あなたは〇〇の専門家です。本日は△△について相談します」といった形で前提を明示すると、以降の応答が一貫しやすくなります。
「あなたは企業向け研修のプランナーです。今回は生成AIに関する講座内容の相談をします」
「受講対象は30代のビジネスパーソンで、AIの初心者を想定しています」
このように、会話の背景と目的を最初に共有することで、モデルがやり取りの意図を正しく理解しやすくなります。
資料や履歴を整理して提示する
ChatGPTに大量の情報を一度に渡すのではなく、「こちらが前提資料①です」「次に資料②をご確認ください」といった形で段階的に提示することで、内容の理解が格段に向上します。
悪い例:FAQや要件定義、仕様書などをまとめて一括投入
良い例:「まずこの資料を読んでください。理解できたら『OK』と返してください」
加えて、表形式や箇条書きなど整理された構成で情報を提示することにより、文脈の明瞭化と読み取り精度の向上にもつながります。
不要な情報を省き、必要な情報だけを残す
過去の会話履歴や使い終わった資料が残っていると、AIの応答が曖昧になったり、すでに不要な情報に引っ張られることがあります。
そのため、必要に応じて「新しいチャットを始める」、あるいは「この情報は不要です」と明示することが有効です。
さらに「どの情報を読み込んだうえで」「何を出力すべきか」を具体的に伝えることで、AIは目的に沿った応答をしやすくなります。
1枚の設計シートとしてスクリプトをまとめる
会話が複雑化してきたときは、内容を「スクリプト」や「シナリオ」の形式で整理し直すのがおすすめです。
これにより、プロジェクトの要件書やAIへの明確な指示としても活用できます。
「対象読者:AIに関心はあるが初心者のビジネスパーソン」
「目的:ChatGPTを使ってAI関連の記事を円滑に執筆できるようにする」
「希望する出力:記事構成 → セクション別本文 → SEO観点の提案」
こうした構造的な設計により、ChatGPTは単なる質問相手から、信頼できる“コラボレーター”として機能するようになります。
プロンプト設計とコンテキスト設計の併用術

プロンプトとコンテキストは補完し合う存在であるともいえます。
そのため、併用の意義や実務での活用法を理解することで、生成AIの出力精度を一段と高められます。
プロンプトとコンテキストをセットで考える
AIに的確な指示を出すには、プロンプト(その場の命令)とコンテキスト(背景や前提)をセットで設計することが重要です。
たとえば、「記事を書いて」とだけ伝えても、AIはトーンも対象読者も分からず、ばらつきのある出力になります。
しかし、「初心者向けに」「ビジネス用語を避けて」などの文脈を先に設定すれば、プロンプトの精度も一気に向上します。
プロンプトは「指揮棒」、コンテキストは「楽譜」として例えた場合、両者を連携させてこそ、AIは“意図通りに”動き出します。
業務での応用例:FAQ自動化やレポート生成
プロンプトとコンテキストの併用は、業務にも非常に役立ちます。
たとえば、FAQの自動生成では「想定ユーザー」「質問カテゴリ」「口調」などのコンテキストを設計した上で、「この内容をQ&A形式にしてください」とプロンプトを出すことで、一貫性のある出力が可能になります。
レポート作成でも目的や読み手、データの要約方針を先にコンテキストとして与えると、プロンプトだけでは得られない高精度なドキュメントが得られます。
日々の定型業務こそ、AIと併用設計の相性が抜群です。
チームで再利用できるテンプレートの設計法
AI活用をチームで標準化するには、プロンプトとコンテキストを組み合わせたテンプレート設計が効果的です。
目的・想定読者・出力形式などの「共通コンテキスト」を明文化し、それに対して「生成したい内容」を変数化したプロンプトをセットにします。これにより誰でも安定した品質でAIを活用できます。
テンプレート化により属人性が減り、チーム全体の生産性と再現性が向上するのです。
コンテキストエンジニアリングの活用事例

コンテキストエンジニアリングは、情報の整理と提示方法を最適化することで、AIの業務活用を加速させます。
ここでは、カスタマーサポート業務やFAQ自動化、RAGとの連携といった実用的な活用例を紹介します。
カスタマーサポート業務でのRAG機能検証
日立は「日立サポート360」のカスタマーサポート業務でRAGの機能検証を実施し、ITシステムへの生成AI活用を実現しました。
当初は誤回答率66%、使える回答はわずか24%だったものが、複数の領域でRAGを高度化することで7割以上の回答精度を達成したのです。
具体的な取り組みとしては、クエリの最適化(質問の分割・拡張)、外部知識の適切な取得(検索ツールの組み合わせ)、情報の整理・順位付けを行いました。
さらに情報源の提示機能も開発し、エキスパートによるチェックを行うことで、高い精度が求められる業務での生成AI活用を可能にしました。
誤回答を大幅に削減し、7割以上の回答精度を実現しました。さらに、回答の中に誤りがある恐れを考慮し、その根拠となった情報源を提示するなど、誤回答の発生を前提とした、追加のRAG機能も開発し、「日立サポート360」における一部業務での生成AI活用を果たしました。
出典:株式会社日立ソリューションズ
コンテキストエンジニアリングを活用したマルチモーダルAIの開発
トヨタは「大部屋方式」にちなんだAIシステム「O-Beya」を開発し、ベテランエンジニアの知識継承とパワートレーンの開発効率化を実現しました。
このAIシステムは、9つの専門AIエージェントが協働し、複数の観点から統合的な回答を提供する仕組みになっています。
技術面では、Microsoft Azure OpenAI ServiceとRAG技術を活用し、設計報告書から手書き文書まで多様なデータを文脈理解可能な知識ベースとして構築しています。
2024年1月の運用開始後、約800人のエンジニアが月数百回利用しており、従来の文書検索に要していた膨大な時間が大幅に短縮されています。
現在の O-Beya システムには 9 つの AI エージェントが実装されており、振動の専門家から燃費の専門家まで、様々な分野をカバーしています。ユーザーは質問内容に応じて、複数のエージェントを同時に選択することができます。
出典:https://news.microsoft.com/ja-jp/features/241120-toyota-is-deploying-ai-agents-to-harness-the-collective-wisdom-of-engineers-and-innovate-faster/
まとめ
コンテキストエンジニアリングは、生成AIの出力精度や業務適用性を大きく左右する「情報設計の技術」です。
プロンプトだけでは対応が難しい複雑なタスクも、適切な情報の収集・圧縮・配置によって高精度かつ再現性のある応答が可能になります。
FAQ自動化やナレッジ共有、RAG連携といった実用例からも分かるように、今後はプロンプトとコンテキストを一体で設計する視点が、あらゆるAI活用の土台となっていくでしょう。
