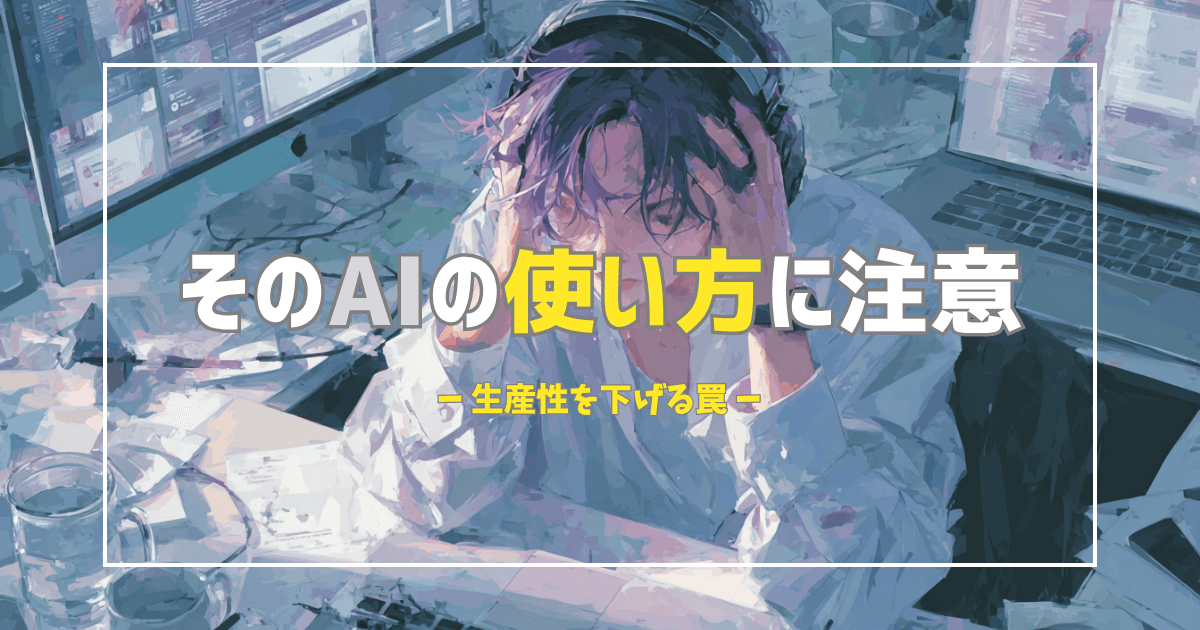
この記事は、Podcast「AI未来話」のエピソード「#2-3 そのAIの使い方は注意!生産性を下げる罠」を再構成した内容をお届けします。
AIの普及に伴い、多くの人が日々の業務やプライベートでAIツールを活用するようになりました。AIをうまく使いこなすことで業務効率は飛躍的に向上すると期待されていますが、一方でその活用方法を誤ると、逆に生産性を大幅に下げてしまうことがあります。
今回は実際にAIを業務で使っている中で気づいた「AIの使い方に潜む生産性低下の罠」について詳しく語り合いました。「疑似マルチタスク」という新たな問題を取り上げながら、その原因と対策を掘り下げていきます。
AI活用で陥る「疑似マルチタスク」の罠
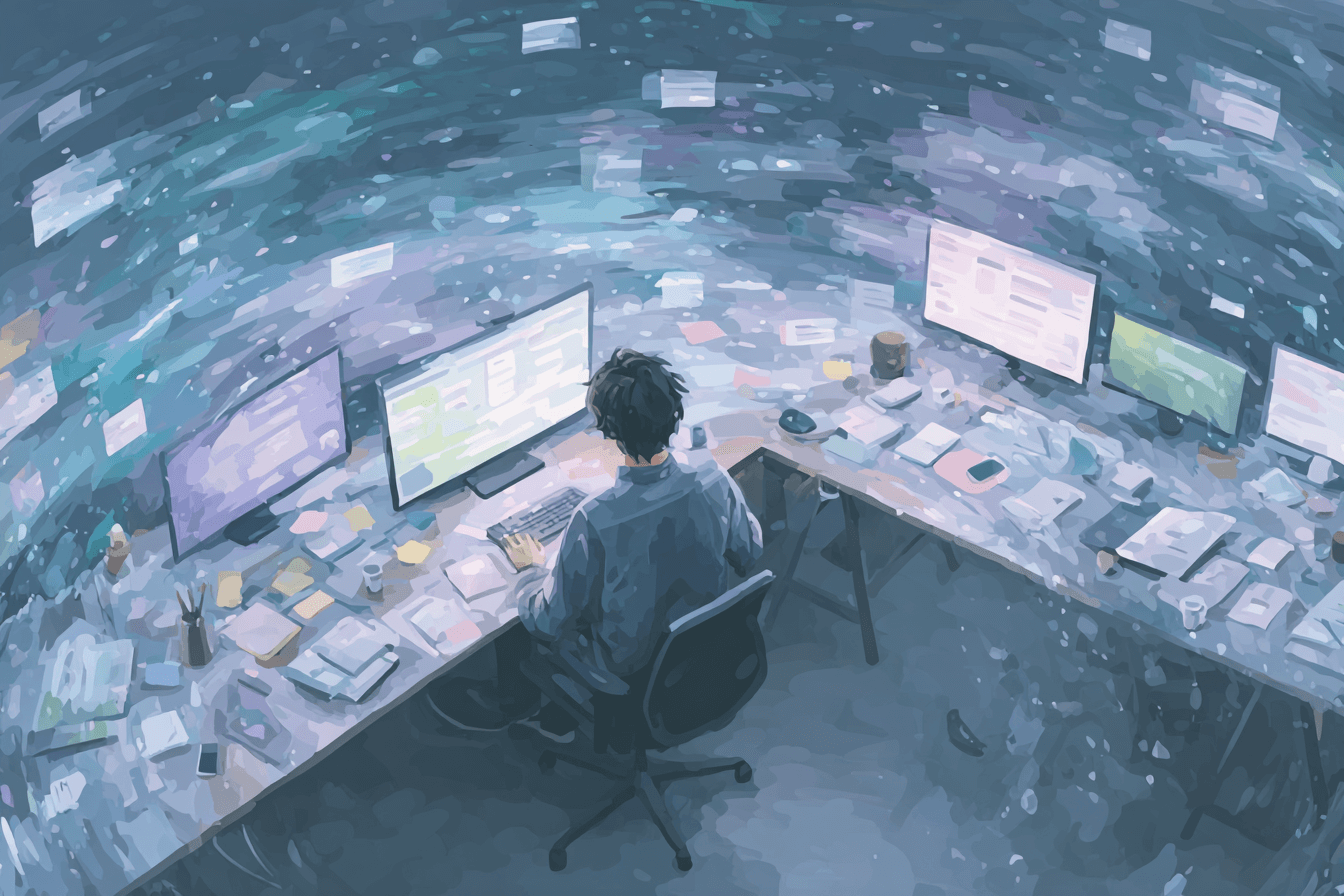
ChatGPT やその他の生成AIツールを使っていると、返答が返ってくるまでの “待ち時間” が発生します。この待ち時間がもったいないと感じるあまり、つい他の作業を並行して行ってしまう人も多いのではないでしょうか。
実はこれが大きな落とし穴になっており、AI活用時に誰もが陥りやすい 「疑似マルチタスク」 という罠について説明します。
「疑似マルチタスク」とは何か?
――今回のテーマは「AIを使った時に生産性が下がってしまう」ということですが、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
「はい、端的に言うと『疑似マルチタスク』という状態が発生します。例えば ChatGPT を使っていると、特に推論特化モデルは回答を待つ時間が長くなりますよね。
特に o3-pro だと 20〜30分かかることもあります。その間にメールを返信したり、SNS をチェックしたり、他の仕事に手を出したりしてしまいがちです。一見生産的に思えますが、実際は作業を同時に進めているのではなく、ただ単にタスクを切り替えているだけなんです」
――確かに待ち時間を効率よく使いたくなります。むしろそれが普通の感覚かもしれません。
「そうなんです。ただ、この行動が生産性を著しく下げる要因になることを、過去の研究 が明確に示しています。私自身も『マルチタスクは良くない』と日頃から言っているはずなのに、無意識のうちにやっていました。多くの人も知らず知らずのうちに同じ罠にはまっているのではないかと思います」
マルチタスクが招く認知的コスト
――マルチタスクはよくないという話は以前から耳にしますが、具体的にどういった理由で生産性が下がるんでしょうか。
「そもそも、人間の脳は並列処理が得意ではありません。複数のタスクを同時にこなしているように見えても、実際には高速でタスクを切り替えているだけです。この切り替えの過程で認知的コストが発生し、注意力が細切れになってしまいます」
――なるほど、複数の作業を同時に行っていると思い込んでも、実は切り替えのたびに負担が発生しているわけですね。
「ワシントン大学ボッセル校(UW Bothell)のソフィー・ルロイ博士は、タスクを切り替えた後も前のタスクの痕跡が残る注意残像(Attention Residue)を提唱しています。たとえばメールを書きながら途中で電話に出ると、電話が終わっても頭の中にメールの文脈が残ったままで、次の作業への集中が削がれる――そんな現象です。
さらに、ミシガン大学の認知心理学者デイビッド・E・メイヤー氏らの研究では、タスクを切り替えるたびに最大40%もの生産時間が失われることが示されています。頻繁なスイッチングはミスの増加や作業品質の低下も招きます。これが『疑似マルチタスク』の怖さです」
集中力回復にかかる想像以上のコスト
――タスクの切り替えには時間的ロスも大きいとのことですが、具体的にどのくらいの時間が失われるのでしょう?
「カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)の調査によると、一度途切れた集中力を元に戻すには平均23分かかります。ChatGPTでの待ち時間に通知をチェックしただけでも、この“23分”のリセットが発生し得るわけです」
――23分というのは思っていた以上に大きいですね。それが一日に何度も繰り返されるとなると、かなりの損失になりそうです。
「実際、harmon.ie 社の多国籍調査では、回答者の約3分の2が1日30分〜2時間を中断対応に費やし、21%は2時間超を失っていると報告されています。通知一つが隠れた時間泥棒になり得るということです」
――そういえば平岡さんは集中したい時にイヤホンをつけたりしていますよね。
「周囲に“話しかけないで”と示すためのシンプルな仕組みですね。環境をコントロールして余計な刺激を遮断することは非常に有効です」
記憶の定着力が低下するリスク
――マルチタスクによる認知的コストには他にも影響があるのでしょうか?
「タスクを頻繁に切り替えると、脳が情報を整理・定着させる時間が奪われ、学習内容の記憶定着率まで低下します。さらに、注意が分散するためフロー状態(ゾーン)にも入りにくくなり、創造性や深い集中が阻害されるんです」
――フロー状態は理想的な集中状態ですよね。それを失うのはかなりの損失ですね。
「まさにマルチタスクを避けることは、生産性だけでなく集中力・記憶力・創造性を守るためにも重要です。AIと共生する時代こそ、この事実を踏まえてAIの使い方を設計すべきだと考えています」
フロー状態(ゾーン)に入りにくくなる
――さきほど「フロー状態」の話が出ましたが、これは具体的にどんな状態を指すんでしょうか?
「フロー状態とは、ハンガリー系米国人心理学者 ミハイ・チクセントミハイ(Mihály Csíkszentmihályi) が提唱した概念で、いわゆる“ゾーンに入る”状態を指します。
作業に完全に没頭し、時間を忘れて集中している状態ですね。例えば、趣味に没頭して気づいたら数時間経っていた——そんな経験をしたことがある方も多いと思います」
――確かにありますね。そういう時って、すごく効率よく作業が進んだりしますよね。
「その通りで、フロー状態は生産性や創造性が最大限に高まっている状態なんです。ただし、この状態に入るまでには一般に10〜15分程度の集中が必要とされます。そして、マルチタスクのように頻繁にタスクを切り替えたり、メールやSNSの通知が来たりすると、その集中が途切れてフローに到達しづらくなるんです」
タスクの性質を見極める重要性
――ここまでの話でマルチタスクのデメリットがかなり明確になりましたが、すべての状況でマルチタスクが悪いわけではないのでしょうか?
「良いポイントですね。実はタスクの性質をきちんと見極めることが非常に重要です。コードを書いたり資料を作成したりする作業は、一人で集中すべきタスク。一方で、アイデア出しやチームの方向性を決めるような作業はコミュニケーションが不可欠です」
――なるほど。そう考えると、タスクの特性に応じた環境づくりが求められますね。
「はい。『集中すべき作業』と『コミュニケーション重視の作業』を明確に分けることで、それぞれ最適な環境を整えられます。
AI特有の生産性低下要因
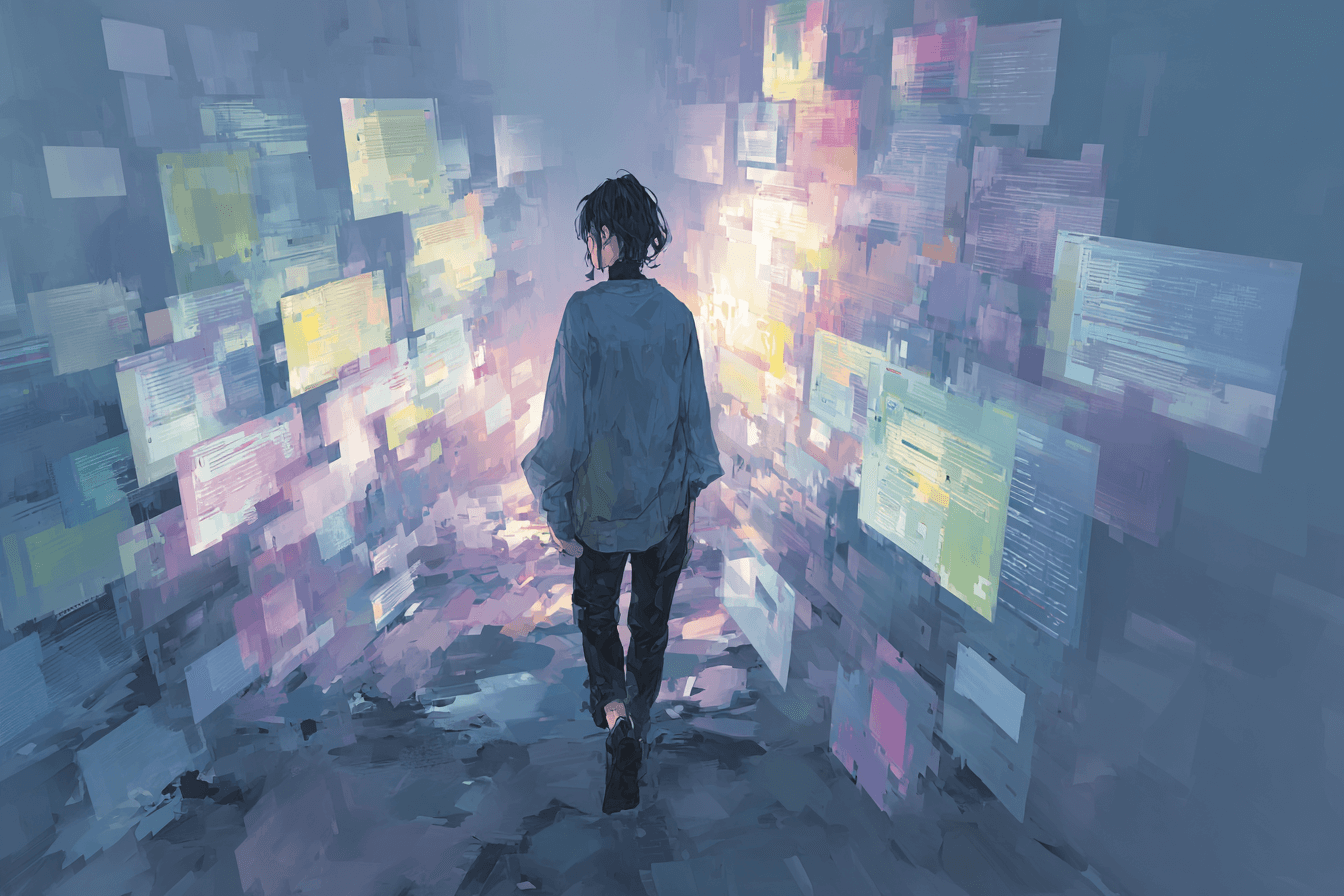
AI特有の注意点を知らずに利用していると、意識せずに多くの時間と集中力を奪われる可能性があります。ここではAIを使用する際に陥りやすい罠について具体的に解説していきます。
ハルシネーション見落としのリスク
――AIを使う上でのリスクは何がありますか?
「ハルシネーションの見落としがまずあります。ハルシネーションを見抜くには回答を丁寧に検証する必要がありますが、マルチタスクで注意が散漫になると見落としやすくなります」
――確かにAIが出した回答を鵜呑みにしてしまうケースはありますね。
「私自身も経験がありますが『あとで見直せばいいか』と軽く流してしまうと、後に大きな誤りへつながり、修正に余計な時間がかかることがあります。集中力が低下するとハルシネーションの見落としが頻発し、結果的に生産性が下がっているパターンですね」
プロンプト反復で失われる時間
――AIを使う時にもう一つよくある問題として、プロンプトを繰り返し調整することで時間を無駄にしてしまう、ということがありますが、これは具体的にどんな問題でしょうか?
「私もよく陥るのですが『もっと良い回答が欲しい』とプロンプトを微調整し続けるうちに、その微調整自体が目的化してしまうことがあります。
頻繁に文脈やゴールが変わると、マルチタスクと同じような認知的負荷がかかります。明確な基準やゴールがないまま続けると、AIとの対話自体が目的化し、本筋から逸脱してしまうんです。これを防ぐには、事前にゴールと評価基準を定め、その範囲内で対話を進めることが重要になります」
AIに頼り過ぎることで思考力が低下する危険性
――AIがあまりにも便利なので、つい頼りすぎてしまい、自分で考えなくなってしまうということもありますよね。
「これは非常に重要なポイントです。AIが多くの作業を代替してくれるため、“AIに任せておけば安心”という思考停止に陥る人も少なくありません。近年の研究でも、AIツールの多用と批判的思考力の低下との関連が指摘されています。
AIの回答を無条件に受け入れてしまうと、人間本来の思考力や判断力が低下しかねません。AIはあくまで“支援ツール”であり、最終的な判断は人間が担うべきで、仕組みを知り、背景にある情報やバイアスを意識的に検証し、自身の思考を深める材料として活用することが理想的ですね」
生産性を高めるための具体的なAI活用法
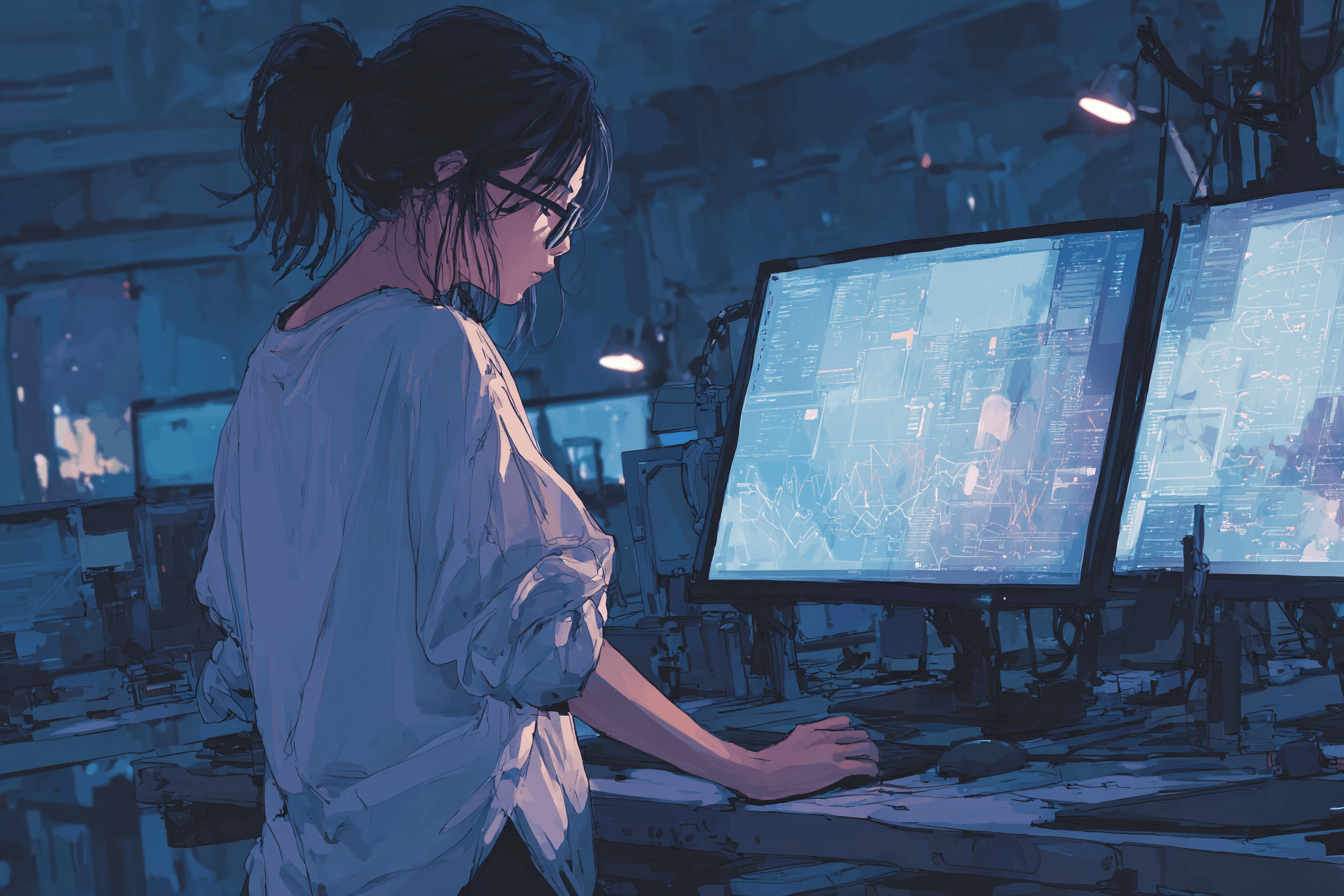
AI活用時の罠を避け、生産性を向上させるためにはどうすればよいのか?実践的かつ具体的な方法を解説します。
タイムブロッキングの重要性
――具体的に生産性を高めるための方法としては、まず何から始めると良いでしょうか?
「まず一つ目は 『タイムブロッキング』 という手法がおすすめです。これは作業内容ごとに明確に時間枠を設定し、他の作業が入り込まないように“ブロック”する方法ですね。テスラ/スペースX の CEO イーロン・マスク氏 が、5分単位 で予定を組む『ファイブ・ミニッツ・ルール』で実践していることでも知られています」
――具体的にはどういった感じで使うのでしょうか?
「たとえば、AI を使って資料を作成する時間を『午前 10 時〜11 時』と決め、その時間には他のことを一切やらないようにします。AI の回答待ち時間があっても、そのブロック内で作業を完結させる意識を持つんです。
タイムマネジメントに関するメタ分析 では、こうした時間管理行動が 職務パフォーマンスとウェルビーイングを中程度に向上させ、ストレスも有意に低減することが示されているそうですよ」
――平岡さんは以前からタイムブロッキングを推奨していましたが、それでもマルチタスクをしてしまったと。
「そうなんです。私のようにはならないでください(笑)それくらい回答までの待ち時間は危険なのです。『1 ブロック=1 タスク』 を徹底することが成功のカギです」
待ち時間を有効活用する「内省・休憩法」
――とはいえ、AI の回答待ち時間は必ず発生しますよね。その時間はどう使うのが一番効率的でしょうか?
「何もしない短い休憩(マイクロブレイク) を意識的に取ることを推奨します。イリノイ大学の研究 では、わずか数十秒の気分転換でも集中力の低下を防げることが示されています」
――ぼーっとするのは意外と正しい行動だったんですね。
「はい。さらに 2022 年の マイクロブレイクのメタ分析 でも、10 分未満の休憩が活力を高め、疲労を減らすことが確認されています」
待ち時間に「仮説」を立てて思考トレーニング
――休息以外に待ち時間の使い方としておすすめの方法はありますか?
「これは個人的なおすすめですが『AI の回答を予測しながら待つ』 ことです。仮説を立てることでプロンプトがどのように挙動するのか、こんな回答がきたらこう返そうとか、予測していない回答が来ると学びが深くなります。実際に学習科学の研究では 自分で仮説を立ててから答え合わせをする行為は理解度を高めることが示されているそうですよ」
――ただ待つだけよりはるかに有意義ですね。
「その通りです。待ち時間が能動的な思考の場になり、AIとの対話が深い学びにつながります」
メモ書きで認知的コストを軽減
――AI の待ち時間を使う場合でも、どうしても他のタスクに移らなければならない時があると思います。その場合は、どんな対策をするとよいでしょうか。
「おすすめしたいのがメモ書きでタスクを区切る方法です。タスク切り替え時に未完了タスクが頭に残り続ける注意残像は先ほど話しましたね。未完了タスクをメモに書き出すことで注意残像を減らすことができます。
もしくは『次に何をするか』を具体的に計画に落とし込むだけでも、認知的負荷が軽減されることがフロリダ州立大学の研究「Consider It Done!」(2011)でも示されています」
――具体的にどのようにメモを書けばよいでしょうか。
「難しいフォーマットは不要で『いま何をしていたか』『次に何をするか』の二行を書くだけで十分です。こうしてタスクを“頭の外”に出すことで、まだ終わっていないという心理的モヤモヤを和らげ、切り替え後の集中力が大幅に向上します」
類似タスクのグルーピングで効率化
――他に AI 活用時のマルチタスク負荷を減らす方法はありますか。
「類似タスクをグループ化(バッチ処理)するというのもあります。ハーバード・ビジネス・レビューの “Toggle Tax” 調査では、アプリを切り替えるたびに年間約5週間分の作業時間を失うと報告されています。似た性質のタスクを塊で処理すれば、このコンテキスト・スイッチング損失を最小化できます」
――具体的なグループ化の方法として、どのようなやり方がありますか。
「たとえば記事制作なら『企画→取材→執筆→校正』を工程ごとにまとめて処理する。ProductPlanの解説記事でも、同種タスクのバッチ処理が集中力と生産性を高めると推奨されています」
AIへの依頼は「一発」でまとめる
――AI を使う際に、他にも生産性を高めるためのポイントはありますか。
「AI への依頼を1回でまとめることです。生成 AI は裏側でマルチスレッド処理を行うため、翻訳・要約・構造化など複数タスクを1つのプロンプトで同時依頼した方が高速です。
実際、並列リクエストで ChatGPT の応答速度を向上させる事例が開発コミュニティで多数共有されていますし、細かく依頼を分けると、そのたびに回答待ちが発生し、人間側の待機コストと認知的切り替えコストが増えるのでコスパが悪いです」
――つまり AI を最大限に活用するためには、人間側が AI に合わせた指示を出す必要があるんですね。
「まさにそうです。まとめ依頼で待ち時間を短縮しつつ自身はシングルタスクに集中、マルチタスクはAIにお願いすることが高い集中と生産性を維持できます」
「通知オフ」で集中力を守る
――他にもありますか?
「最もシンプルで効果が大きいのが通知をオフにすることです。米カリフォルニア大学アーバイン校の グロリア・マーク教授の調査では、オフィスワーカーは1日平均74 回メールをチェックしているそうです。
これも先ほどのタスク切替と同様に、元の作業に戻るまで平均23分かかりますからね。1 日の相当な時間が通知で作業ロスしています」
――そんなに大きな影響があるとは驚きですね。
「これは基本中の基本ですが、やはり効果は高いです。通知は悪魔なので、遮断をして待ち時間を内省・仮説立て・小休憩に充てて生産性とストレスを和らげていきましょう」
まとめ
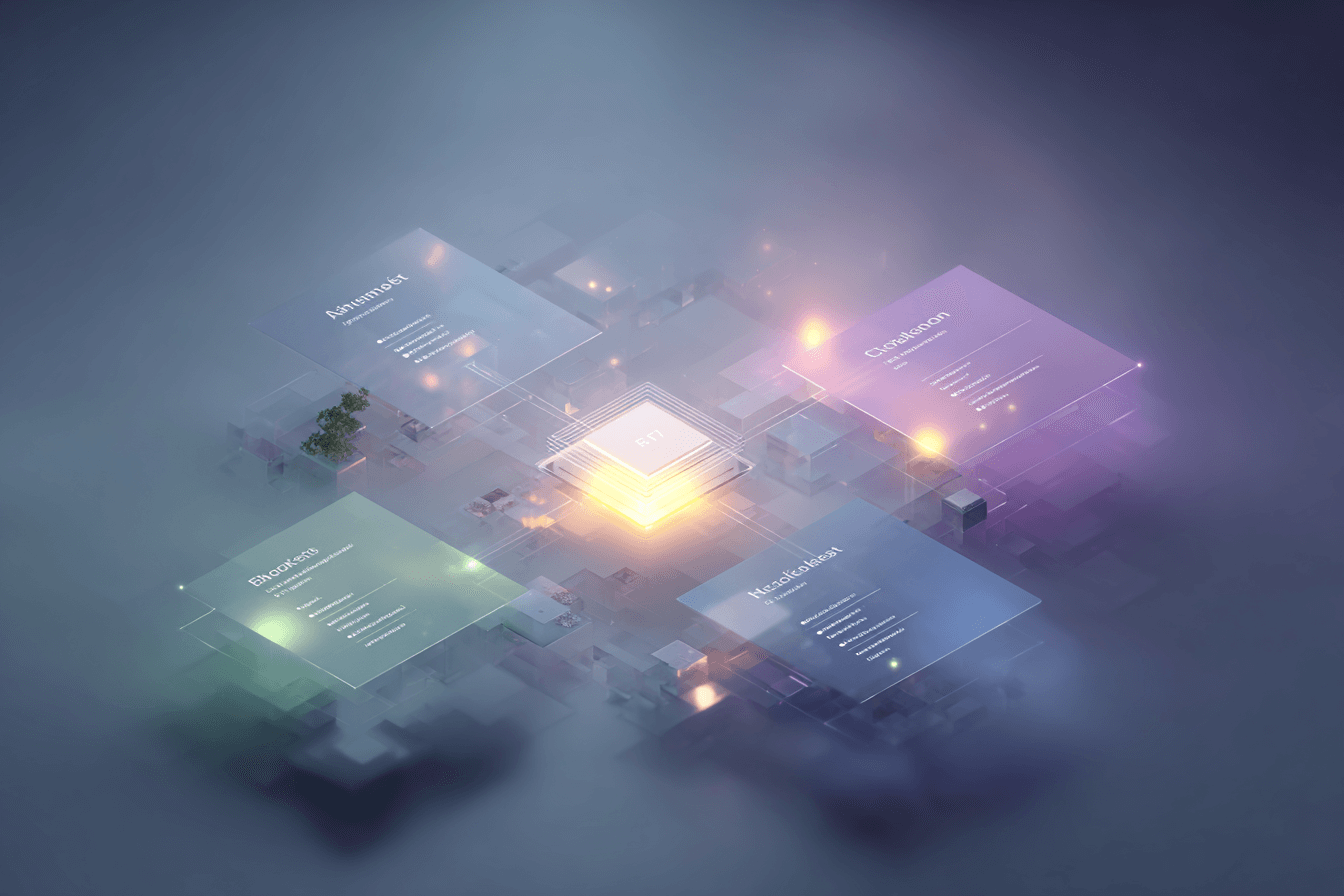
今回のエピソードでは、AIの使い方によって生産性が下がる罠と、その回避方法について解説しました。重要なポイントは以下のとおりです。
- 人間はマルチタスクが苦手であり、頻繁なタスクの切り替えが集中力や記憶力、作業品質を大きく低下させる。
- AI利用時の待ち時間に他の作業を入れる「疑似マルチタスク」は、実は非効率である。
- マルチタスクを避けるためには「タイムブロッキング」「内省・休憩」「仮説立て」「メモ書き」「類似タスクのグルーピング」「通知オフ」といった具体的な手法が有効である。
- AIへの依頼は並列処理が得意なAIの特性を活かして一度にまとめるといい。
- 人間はシングルタスクに集中し、マルチタスクはAIに任せるという協働の形を目指すことで、真の生産性向上を実現できる。
これらを意識して実践することで、AIを最大限に活用しつつ、人間が本来持つ集中力や創造力を存分に発揮できるようになります。日々の仕事や生活にぜひ取り入れてみてください。
